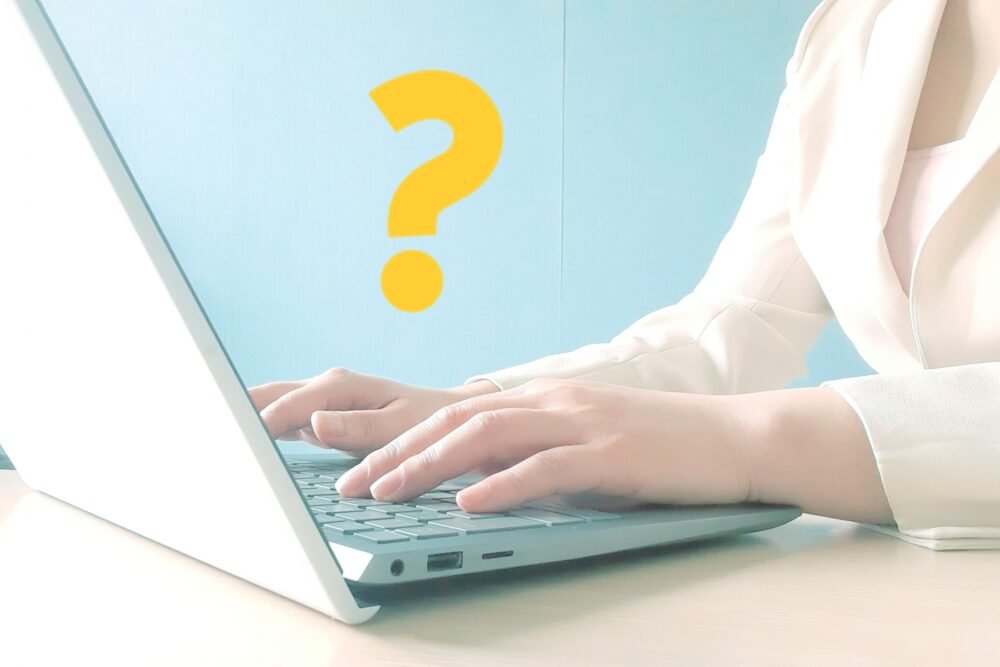SESとは何?Slerとの違い、SES企業でのエンジニアの仕事内容を徹底解説
ITエンジニアの働き方に関する用語である「SES」。ITエンジニアを目指す方なら、見聞きしたことがあるのではないでしょうか?
本記事では、SESとは何か、SESと派遣やSIとの違い、雇用関係や契約形態、仕事内容とメリット、デメリットについて解説しつつ、未経験者がSES企業に転職する方法やSESに関するQ&Aにも触れています。
SESについて知りたい方、SES企業での働き方に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
SESとは何?
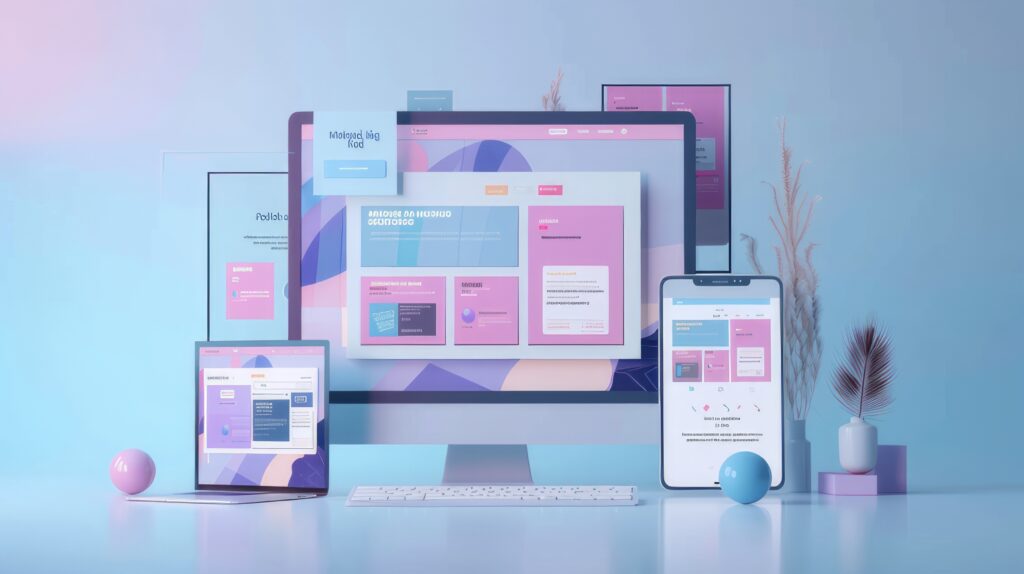
SESとは、「System Engineering Service」の略称であり、SES企業がクライアントに対して技術提供をするサービスのことを指します。
SES企業にはエンジニアが所属しており、クライアントの要望に合った技術を持つ人材を提供する仕組みとなっています。
通常のシステム開発ではクライアントからのオーダーに対して完成したシステムを納品するケースが一般的ですが、SESではシステムの完成義務が生じないケースがほとんどです。
あくまでSES企業が提供するのは技術であり、開発に関する支援が業務内容となる点が特徴として挙げられます。
システム開発における契約形態とSES契約の関係
一般的にシステム開発における契約形態は請負契約と準委任契約の2つに分けられ、以下のような違いがあります。
システム開発業務において、SES契約は場合によっては請負契約になりますが、基本的には準委任契約に分類されます。
| 請負契約 | 成果物の完成義務があり、成果物の品質や仕様などを発注内容と比較する検査を経て、報酬が支払われる |
| 準委任契約 | 業務遂行に対して報酬が支払われ、成果物の完成義務は生じない |
請負契約ではシステム開発による成果物の完成と納品が報酬の対価となるのに対し、準委任契約では業務遂行そのものに対して報酬が支払われるため、成果物の完成や納品は求められません。
契約内容によって請負契約にあたるのか準委任契約にあたるのかが変わるため、契約時には必ず報酬に対して求められる対価について確認する必要があります。
システム開発の業界構造とSES企業
日本の中規模以上のシステム開発では、複数の企業が1つのシステム開発プロジェクトに対して以下のように携わるのが一般的です。
- 大元のクライアントが元請け企業に開発を発注
- 元請け企業は要件定義や企画をおこなう
- 元請け企業が必要に応じて二次請け企業へプロジェクトの一部を委託
- 二次請け企業がプロジェクトの進行管理をおこなう
- 二次請け企業が必要に応じて三次請け企業へ一部の業務を委託
上記の流れでは、二次請け企業と三次請け企業がSES企業であることが多く、技術のみを上位クライアントへ提供する形となります。
SES契約と派遣契約の違いとは?

SES契約と派遣契約には、以下のような違いがあります。
| SES | 派遣 | |
|---|---|---|
| クライアントとエンジニア間の指揮命令関係 | なし | あり |
| クライアントと所属企業※の関係 | SES契約(準委任契約) | 労働者派遣契約 |
| 所属企業との関係 | 雇用関係や業務委託契約 | 雇用関係 |
※ここではエンジニアと契約を結んでいる派遣会社やSES企業を「所属企業」として表記しています。
SES契約と派遣契約はよく似た契約ではあるものの、クライアントとの指揮命令関係の有無や所属企業とクライアントの契約内容などに違いがあります。
特に、エンジニアとクライアント企業との指揮命令関係では、SESの場合はクライアント企業はエンジニアに指揮命令を下すことができず、エンジニアはあくまで所属するSES企業との契約内容を遂行することが仕事となっています。
SESとSI(SIer)の違いとは?

SESに似た用語に「SI」があります。SIとは、「System Integration(システムインテグレーション)」の略称であり、SIを主な業務とする企業は「SIer(エスアイヤー)」と呼ばれます。
SESと比較すると、SIには以下のような違いがあります。
| SES | SI | |
|---|---|---|
| 契約形態 | エンジニアの業務遂行が報酬の対価となる | システム開発全般の成果物に対して報酬が発生する |
| プロジェクトへの参加形態 | SIerと契約し、SIerに対してエンジニアの技術を提供する形でプロジェクトへ参加する | システムの開発~保守・運用までをまとめて請け負うことが多く、クライアントと直接契約を結んだり他のSIerの下請けとして参加したりする |
SESが技術を提供する形であるのに対し、SIはシステム開発や運用・保守を請け負います。
報酬の発生についても、SESは業務遂行が報酬の対価となるのに対してSIは成果物の納品が報酬の対価となっています。
課題解決支援という点は共通ですが、SESとSIは活用される目的や役割に違いがある点を理解しておきましょう。
SES企業におけるエンジニアの雇用関係と契約形態

SES企業におけるエンジニアの雇用関係と契約形態には、主に以下の2種類があります。
- SES企業と雇用関係にあたる会社員として働くエンジニア
- SES企業から業務委託を受けるフリーランスのエンジニア
会社員として働くエンジニアは、クライアントのプロジェクトに参加していなくても通常の給与を受け取れます。また、社会保険や福利厚生といった会社員特有の待遇が受けられるのも特徴です。
一方でフリーランスのエンジニアは、参加するプロジェクトごとに定められた期間で技術を提供し、報酬を受け取ります。プロジェクトに参加していない期間は報酬が発生しません。
またフリーランスの場合、社会保険や福利厚生などはあまり望めないものの、主体的に案件を選べるという特徴があります。
SES企業におけるエンジニアの仕事内容について

SES企業におけるエンジニアの仕事内容には、以下のようなものがあります。
| 業務の種類 | 業務内容 |
|---|---|
| システム開発 | 要件定義・プログラミング・テストなど |
| 技術サポート | システムのトラブルシューティング・ユーザートレーニングなど |
| プロジェクト管理 | プロジェクトの進行管理・リソース管理・タスク管理など |
| テクニカルリサーチ | 市場動向や技術動向のリサーチ・最新テクノロジーのリサーチ・クライアントやプロジェクトへの提案と情報提供 |
| ドキュメント作成 | 要件定義書、設計書、ユーザーマニュアルの作成など |
実際の業務内容については、SIerなど他の契約形態のエンジニアと大きな違いはありません。
一般的に、SES企業のエンジニアは上記のような仕事をSIerエンジニアなどと共同でおこなっていきます。
SES企業でエンジニアとして勤務するメリットはある?

SES企業でエンジニアとして働く場合、以下のようなメリットがあります。
- 未経験でも採用されるチャンスが多い
- 色々なプロジェクトに参加できスキル習得の機会が多い
- 主体的に案件を選べる
- 企業や人と広い繋がりを持つことができる
それぞれ詳しく解説します。
未経験でも働きやすい
ITエンジニアには専門的なスキルが求められるため、就職には実務経験が必要であるケースが多いですが、SESなら未経験でも採用のチャンスがあります。
多くのプロジェクトを抱えるSES企業では、スキルレベルに合わせて案件を繋げてくれるため、未経験者であっても採用のチャンスがあるのです。
また、SES企業では未経験者向けの教育や研修プログラムに力を入れていることもあり、プロジェクト参加に必要な知識やスキルの習得を企業側でサポートしてくれるケースも珍しくありません。
色々なプロジェクトに参加できる
SESエンジニアはさまざまなプロジェクトに参加する機会があるため、実務を通してスキルを習得できる機会が多いという特徴があります。
異なる業界や企業のプロジェクトに関わることで経験を積むことができ、幅広い領域や技術に触れられるのはSESならではのメリットです。
主体的に案件を選べる
エンジニアが主体的に案件を選べる場合があるのも、SESのメリットです。
多くのプロジェクトを抱えるSES企業であれば、エンジニアが主体的に案件を選べることも珍しくありません。
またプロジェクトの期間に縛られず単発的に参加するケースもあるため、希望によって案件を移動できるのもSESエンジニアの特徴です。
広い繋がりを持てる
SESエンジニアとして働いていると、さまざまなクライアント、幅広い領域のプロジェクトに関わることになり、人や企業と広く繋がりを持つことができます。
さまざまな企業を渡り歩きながら仕事をするため、コネクションが広がるのはSESエンジニアとして働く大きなメリットです。
SES企業で勤務するエンジニアにはデメリットも

メリットの多いSESエンジニアですが、一方でデメリットもあることを理解しておきましょう。
- 単発的な参加が多いためシステムの全体像が見えづらい
- 短期案件が多く一貫したキャリアを築きにくい
- プロジェクトごとに職場環境が変わり安定感がない
- 収入が一定ではなく低かったり不安定だったりする
- 自社との関わりが希薄で帰属意識を持ちにくい
ここでは、SES企業で働く際のデメリットについてそれぞれ詳しく解説します。
システムの全体像が見えにくい
SESとしてプロジェクトに参加する場合は単発が多く、システム全体が見えにくいデメリットがあります。
自分が一体何のシステムを開発しているのか把握できず、やりがいを感じにくいと感じるエンジニアは少なくありません。
短期間の案件であっても、自分が関わるプロジェクトのシステム全体をきちんと把握するようにしましょう。また、チームメンバーと積極的にコミュニケーションをとることで仕事のモチベーションも維持しやすくなります。
一貫したキャリアを築きにくい
SESエンジニアは短期でプロジェクトを転々とする特性上、一貫したキャリアを築きにくいというデメリットがあります。
1つの分野で一貫したキャリアを築きたいと考えている場合は、なるべく同じ領域の業務を請け負うようにするなどの工夫が必要です。
職場環境に安定感がない
SESエンジニアはプロジェクトごとに異なる職場環境を渡り歩くため、安定した環境で仕事ができません。
最近ではリモート可の案件もあるため、職場環境をなるべく安定させたい方はフルリモート案件を積極的に請け負うと良いでしょう。
収入が安定しない
SESエンジニアの収入は、案件によって低くなったり高くなったりと不安定です。同じ業務内容であっても、正社員のSEと比較すると報酬が低くなることもあります。
また継続的に同程度の報酬の案件を受け続けられるという保証がないため、常に収入が安定しない不安を抱えることになる点は大きなデメリットでしょう。
収入が安定しない分、報酬を計画的に使う工夫をしたり長期案件を選んだりすることが大切です。
自社との関わりが希薄になる
SESエンジニアは自社よりも他社などで案件に携わる時間が多いため、自社への帰属意識を持ちづらくなりがちです。
SES企業で働きつつ自社に対する帰属意識を持ち続けるには、社内のイベントやミーティングに積極的に参加して他の社員とコミュニケーションをとるようにすると良いでしょう。
未経験者がSES企業に転職する方法2選
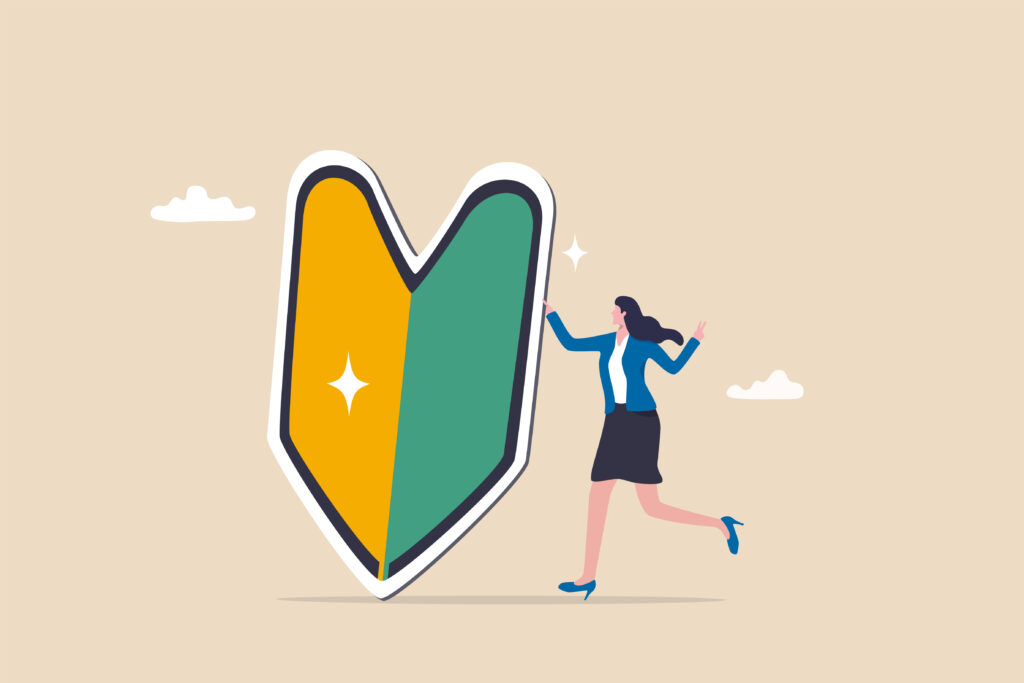
未経験者がSES企業に転職するには、主に以下の2つの方法があります。
- キャリアサポートが手厚い通信制大学やスクールに通う
- 資格などを通じてハイレベルなスキルを身につける
それぞれ詳しく解説します。
通信制大学やスクールに通う
未経験者の場合、キャリアサポートが手厚い通信制大学やスクールに通うことでSES企業に転職しやすくなります。
最近では仕事と両立しやすい完全オンラインの通信制大学やプログラミングスクールもあるため、今の仕事を続けながら通うのもおすすめです。
通信制大学やスクールで基礎から知識と技術を身につけたうえで、キャリアサポートを活用して優良なSES企業に転職しましょう。
開志創造大学 情報デザイン学部では、最先端の情報技術を駆使するエンジニアを目指すことのできる「先端ITコース」があるので、エンジニアを目指して知識や技術を身につけたいという方におススメです!
ハイレベルなスキルを身につける
資格取得などを通じてハイレベルなITスキルを身につけることで、未経験でもSES企業に転職しやすくなります。
基本的なITスキルはもちろんですが、よりハイレベルな資格を取得すれば未経験エンジニアでもSES企業で案件を紹介してもらいやすくなるでしょう。
IT業界で役立つ資格は「IT業界で求められるスキルを紹介!取得方法や必要な理由も解説 」で紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
SES企業のエンジニアにまつわるQ&A

SESで働くのはやめたほうが良いですか?
SESで働くのはやめたほうが良いと言われることがありますが、そのように言われる主な理由には収入の不安定さなどが挙げられます。
ただし、ハイレベルなスキルや実績を持つエンジニアは単価の高い案件を請け負うことも可能であるため、一概に収入が低いとは言えません。
不安定であることは確かですが、それを理由にSESはやめたほうが良いとは言いきれないでしょう。
SESエンジニアの年収はいくらですか?
Geekly(ギークリー)の調査では、SESエンジニアの平均年収は約460万円です。
国税庁が公表している給与所得者全体の平均年収は458万円なので、平均的な年収であると言えます。
参考:SESの年収は?年収を上げる方法やキャリアプランを解説 | GeeklyMedia(ギークリーメディア) | Geekly(ギークリー) IT・Web・ゲーム業界専門の人材紹介会社
SESはどんな人に向いていますか?
SESに向いているのは、以下のような方です。
- 色々なプロジェクトを経験したい
- コミュニケーションスキルを向上させたい
- プロジェクトマネジメントに興味がある
- 幅広い領域の業務に携わりたい
SESは色々なプロジェクトを転々とするため、経験を積みたい方やコミュニケーションスキルを向上させたい方、幅広い領域の業務に携わりたい方におすすめです。
また、プロジェクトマネジメントを経験する機会もあるためマネジメント業務に興味がある方にもおすすめです。
エンジニアを目指すなら 開志創造大学 情報デザイン学部がおすすめ!
開志創造大学 情報デザイン学部は一度も通学することなく大学を卒業することができる通信制の学部です。いつでもどこでも学べるので、仕事などの自分の都合に合わせて自由に授業を受けられるのが特長です。
現代社会において、エンジニアをはじめとする多くの職業・職種で情報に関する知識や技術が求められています。情報デザイン学部では、そんなこれからの時代に必要不可欠な知識を「年間授業料25万円」「1回15分の授業動画」で身につけることができます。
今回の記事に登場したようなエンジニアを目指したい方は、AIなどの最新の情報技術を駆使するエンジニアを目指すことができる「先端ITコース」がおすすめです!
先端ITコースでは、データサイエンスや生成AIなどの情報技術を活用することによって問題発見・分析をおこない、課題解決や価値創造をします。そしてコミュニケーション力と多角的な視点をもって組織においてリーダーシップを発揮できるエンジニアを目指すことができます。
まとめ

エンジニアの働き方の1つであるSES(System Engineering Service)。クライアントに対して成果物ではなく技術を提供する形で仕事をする働き方で、一般的には準委任契約の扱いになります。
SESと似た働き方や言葉に派遣契約やSI(System Integration)がありますが、それぞれSESとは意味が異なるため、きちんと理解しておきましょう。
SESエンジニアは幅広い領域の業務に携わることができ、プロジェクトを渡り歩くことで人や企業との繋がりを広げられるというメリットがあります。
一方で、収入の不安定さなどのデメリットがあることも覚えておきましょう。
未経験者がSESエンジニアになるには、スキルや資格を取得するのがおすすめです。通信制大学やスクールを利用して、基礎からITエンジニアとしてのスキルを身につけるのも良いでしょう。
自由度が高くメリットも多いSESエンジニアとして働き、幅広い経験やスキルを身につけてみてはいかがでしょうか?