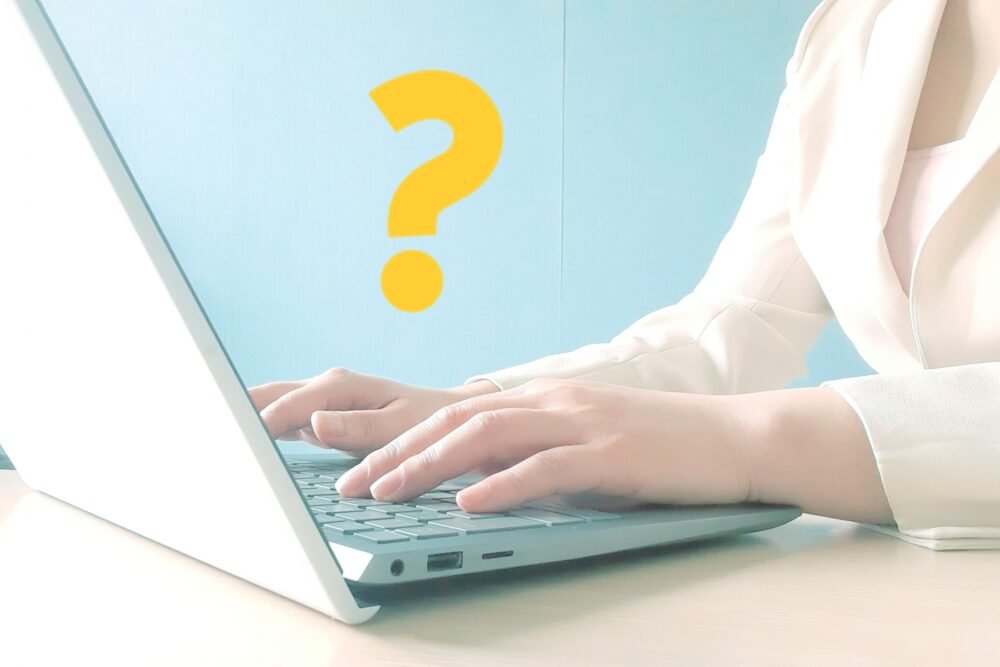AWSとは?何ができるサービスなのか初心者向けにわかりやすく解説
「AWS」の略称で知られている「Amazon Web Services(アマゾンウェブサービス)」。無料で利用を始められるクラウドサービスであり、ビジネスシーンで使われることも多くなっています。
本記事では、AWSの概要、物理サーバーとの違い、できること、ビジネスへの影響、特徴、主要サービス、デメリット、他サービスとの違い、セキュリティ面について解説しつつ、実際にAWSを活用している企業の事例を紹介します。
これからAWSの導入を検討している方、クラウドサービスの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
クラウドについて、詳しく知りたいという方はこちらの記事もおすすめです。
目次
- 1 AWSとは?
- 2 AWSと物理サーバーの違い
- 3 AWSで何ができる?
- 4 AWSの利用により実現すること
- 5 AWSの利用手順
- 6 AWSがビジネスに与える影響とは?
- 7 AWSの10個の特徴
- 8 AWSの料金体系を理解しよう
- 9 【一覧表】AWSが提供する主要サービス9種
- 10 AWSにはデメリットもあるため要チェック
- 11 AWSとMicrosoft Azure・Google Cloudに違いはある?
- 12 AWSなどのパブリッククラウドサービスを選ぶ際のポイント
- 13 AWSのセキュリティ性を高めるポイントとは?
- 14 AWSを導入した企業事例6選
- 15 AWS認定資格について
- 16 クラウドなどの情報知識を学ぶなら、開志創造大学 情報デザイン学部がおすすめ
- 17 まとめ
AWSとは?

AWSとは、「Amazon Web Services」の略称です。
通信販売サイトとして有名なAmazonが運営するクラウドサービスであり、2006年に他社への提供を始めて以来、世界トップレベルのシェアを誇ります。
AWSではさまざまなサービスが提供されており、サーバー作成、システム運用、アプリ開発、情報管理、ビッグデータ分析、セキュリティなどあらゆる機能に優れていることが特徴です。
業界や業種を問わずに使える機能が多数備わっているため、これからクラウドサービスの導入を検討している方にとって特におすすめのクラウドサービスと言えます。
AWSと物理サーバーの違い

AWSはクラウドサービスの1つであり、仮想サーバーと呼ばれるものです。仮想サーバーと対になるものとして、物理サーバーがあります。
ここでは、AWSを含む仮想サーバーと物理サーバーの違いについて表にまとめて紹介します。
| 仮想サーバー | 物理サーバー | |
|---|---|---|
| 概要 | 1台の物理サーバーを複数のサーバーとして利用する | 1台の物理サーバーを1つのサーバーとして利用する |
| 利用シーン | ・リソースを効率的に利用する ・旧システムの環境を引き継ぐ ・災害対策として利用 | ・リソースを占有することで性能を保つ ・小規模環境の構築 |
| 費用 | とても優れている | イマイチ |
| 性能 | 良い | とても優れている |
| 障害による影響 | 広範囲に及ぶ | 小範囲に留まる |
※サーバーとは、インターネットを使ってデータや情報を提供するソフトウェアやコンピューターのこと。
仮想サーバーは1台の物理サーバーを複数のサーバーとして利用し、物理サーバーは1台の物理サーバーを占有して1つのサーバーとして利用します。
リソースを効率的に利用できるため、仮想サーバーのほうがコストパフォーマンスには優れていますが、性能面では1つのサーバーを占有できる物理サーバーのほうが優れています。
また、障害発生時には仮想サーバーのほうが複数のサーバーへ影響が及ぶリスクがあり、物理サーバーのほうは小範囲の影響に留めることができます。
仮想サーバーと物理サーバーにはそれぞれにメリットとデメリットがあり、目的や利用方法によって適切なサーバーを選択する必要があるでしょう。
AWSで何ができる?

AWSには200を超える機能が備わっているので、組み合わせ次第でさまざまなことができます。
- サーバーの構築(Amazon EC2)
- Webサイトの構築(Amazon Lightsail)
- データの保管(Amazon EBS/Amazon S3)
- データベースの利用(Amazon RDS)
- コールセンターの実装(Amazon Connect)
- 仮想デスクトップサービスの利用(Amazon WorkSpaces)
- データ分析(BI)ツールの利用(Amazon QuickSight)
- 機械学習の開発~展開(Amazon Personalize)
- IoTとの連携(Amazon IoT Core/Amazon FreeRTOS)
ここでは、AWSでできる代表的な活用方法を9つ紹介します。
サーバーの構築(Amazon EC2)
Amazon EC2を利用すれば、クラウド上でサーバーの構築が可能です。
状況に応じてスペックを変更できるため、OSの種類やメモリ内容、ハードディスクの容量といった項目を簡単に設定できます。
操作が簡単なので、慣れれば数分で仮想サーバーの構築ができるでしょう。
Webサイトの構築(Amazon Lightsail)
Amazon Lightsail(アマゾンライトセール)では、事前に設定されたアプリケーションを用いて簡単にWebサイトやWebアプリを作成できます。
サーバー構築ができるAmazon EC2よりも自由度は低いものの、必要な機能があらかじめパッケージングされているため初心者でも比較的簡単にWebサイトの構築が可能です。
データの保管(Amazon EBS/Amazon S3)
Amazon EBSは、外付けハードディスクのような感覚でクラウド上にデータを保管できるサービスです。
サーバー(EC2)を停止させてもデータは消滅せずに保存されるため、サーバーの利用を減らしつつデータを管理し続けることができます。
また、Amazon S3(Amazon Simple Storage Servse)はデータの保存、加工、配信が可能な機能であり、インターネット上でのデータ管理が可能です。バックアップやアーカイブなどとしての利用におすすめです。
データベースの利用(Amazon RDS)
クラウド上でデータベースを利用するときには、Amazon RDSが使えます。
データベースサービスではマネージドサービスも一緒に提供されており、アップデートやバックアップなどの保守業務をAWS側で負担してくれるメリットがあります。
AWSはセキュリティ面にも優れているため、重要なデータを保管するのにもおすすめです。
コールセンターの実装(Amazon Connect)
AWSでは、クラウド上でコールセンター機能を実装することができます。
パソコン1台と接続環境さえあれば、すぐにコールセンターを立ち上げられるため、コストを抑えたい中小企業にとっては大きなメリットであると言えるでしょう。
コールセンター機能を実装したいときは、Amazon Connect(アマゾンコネクト)を利用してください。
仮想デスクトップサービスの利用(Amazon WorkSpaces)
Amazon WorkSpaces(アマゾンワークスペース)は、仮想デスクトップサービス(VDI)を構築・利用できるサービスです。
作業環境をクラウド上に保存し、インターネットを介していつでもどこからでも同じ作業環境を利用できます。
外部からのアクセス制限をかければ情報漏洩の対策もできるため、リモート業務などに活用するのもおすすめです。
データ分析(BI)ツールの利用(Amazon QuickSight)
Amazon QuickSight(アマゾンクイックサイト)では、クラウド上でデータ分析ができます。
AWSに格納されたサービスに限らず、csvファイルやExcelファイルを読み込ませてデータ分析を実行することも可能なため、さまざまなシーンへの応用が可能です。
機械学習の開発~展開(Amazon Personalize)
機械学習の開発〜展開までの一連の流れで必要な、モデル開発、学習、推論を実行するサービスとして、Amazon Personalize(アマゾンパーソナライズ)があります。
機械学習モデルを高速で実施し、開発〜展開までの工程を大幅に短縮することが可能です。
ユーザーに合わせた広告配信やニュースのピックアップ配信などに活用されています。
IoTとの連携(Amazon IoT Core/Amazon FreeRTOS)
Amazon IoT Core(アマゾンアイオーティーコア)では、IoT製品との連携が可能です。
モノが受け取った情報をセンサーで感知し、その情報をもとにAWSサービスと連携させられる機能で、情報収集や活用、別のモノへの応用などが可能になります。
またAmazon FreeRTOS(アマゾンフリーアールティーオーエス)ならIoTソリューションの構築も可能です。クラウドやローカルで幅広いデバイスへアクセスできるため、IoTソリューションの構築を実行したい場合におすすめです。
AWSの利用により実現すること
- 必要なときに必要なだけサーバーやストレージを使える
- 高額な機材を購入せず、使った分だけ支払える
- 障害が起きても別拠点に切り替え可能で安心
- データ暗号化やアクセス制御でセキュリティが強い
- AIやIoTなど先端技術を簡単に活用できる
例えば、Webサイト構築・データベース・データ保管・機械学習・コールセンター機能を組み合わせると、Amazonのようなオンラインショップをクラウド上で作ることができます。商品情報や画像を安全に保存し、利用者ごとにおすすめ商品を自動表示、問い合わせもオンラインで対応できる仕組みです。
AWSの利用手順
AWSのアカウント作成は、メールアドレスやパスワード、支払い情報を登録するだけで完了します。作成後は、クラウド上のサービスを自由に利用できるようになります。
STEP1:アカウントの作成
- メールアドレス
AWSの管理者アカウント(ルートユーザー)として使用します。 - パスワード
8文字以上で、大文字・小文字・数字・記号のうち3種類以上を含む必要があります。 - AWSアカウント名
半角英数字で設定します。 - 連絡先情報
氏名、住所、電話番号を入力します。住所は英語表記が必要です。 - 請求情報
クレジットカードまたはデビットカードの情報を入力します。 - 本人確認
SMSまたは音声通話で認証コードを受け取り、入力します。 - サポートプランの選択
「基本サポート(無料)」を選択できます。

STEP2:Amazon EC2の構築
Amazon EC2は、クラウド上で仮想サーバーを作成・管理できるサービスです。必要な性能や台数を自由に選べ、短期間で拡張・縮小できる柔軟なコンピューティング環境を提供しますネットワークを構築する。
①ネットワークを構築する
· リージョンの選択
AWSマネジメントコンソールにログインし、ネットワークやEC2を設置するリージョンを選択します。日本では東京と大阪がありますが、初めて利用する場合はサービスが充実している東京がおすすめです。
· VPCの作成
「VPC」サービスから作成を選び、名称とIPv4のIPアドレス範囲を設定します。IPアドレス範囲は作成後に変更できないため注意が必要です。
· アベイラビリティゾーンの選択
複数のゾーンを選択することで、障害時にも別ゾーンで稼働可能となり、可用性を高められます。
· サブネットや関連設定
パブリック・プライベートサブネット、NATゲートウェイやVPCエンドポイントを必要に応じて設定します。EC2を起動する場合は、少なくとも1つパブリックサブネットを用意します。
· VPC作成完了
設定を確認しVPCを作成します。サブネット名は自動生成されますが、分かりやすい命名ルールで変更すると管理が簡単です
②Amazon EC2を起動する
· 1. マネジメントコンソールにログイン
AWSにログインし、サービス一覧から「EC2」を選択します。
· 2. リージョンの選択
東京など利用地域を選びます。
· 3. インスタンスの起動
「インスタンスを起動」をクリックし、OSの種類(AMI)を選びます。LinuxやWindowsから選択可能です。
· 4. インスタンスタイプの選択
CPUやメモリの性能を選択します。学習用途なら無料枠対象の「t2.micro」などが適しています。
· 5. ネットワーク設定
VPCやサブネットを指定し、必要に応じてパブリックIPを割り当てます。
· 6. ストレージ設定
ディスク容量を指定します。通常は8〜30GBで十分です。
· 7. セキュリティグループの設定
インバウンドルールでSSH(22番)、RDP(3389番)、HTTP(80番)など必要な通信のみ許可します。
· 8. キーペアの作成・選択
インスタンスに接続するための鍵ファイル(.pem)を生成し、安全に保存します。
· 9. 起動
設定を確認し「インスタンスを起動」をクリックすると数分で利用可能になります。
AWSがビジネスに与える影響とは?

AWSを導入し活用することがビジネスに与える影響は、大きく分けると以下の2つです。
- 拡張性(スケーラビリティ)によるリソースの増減
- 俊敏性(アジリティ)による作業時間の短縮
それぞれ詳しく解説します。
拡張性(スケーラビリティ)
AWSを導入することで、必要なリソースを必要に応じて増減することができるようになります。
例えば、ある商品が突然売れ出して完売した際に、すぐに在庫を補充できるようなことが、ITのリソースで再現できます。必要なリソースを適度に増減させることで、効率的に業務を進めることができるでしょう。
俊敏性(アジリティ)
AWSを含むクラウドサービスは、インターネットを始めとするネットワークを使ってサービスを提供しています。
数回のクリックでサーバーを立ち上げ、システム開発や運用を進められることから、高い俊敏性があると言えます。
サーバーを手配する時間などを大幅に短縮できるため、必要なビジネスを素早く立ち上げることが可能です。
AWSの10個の特徴

AWSの大きな特徴は、以下の10個です。
- 使った分だけ料金が発生する従量課金制
- 継続的な値下げでコストを削減できる
- 無料で使える期間がある
- 日本にいながら世界中にシステムを展開できる
- システムの運用保守を全面的にサポートしてくれる
- こまめなアップデートによって常に利便性を高め続けている
- 高いセキュリティ対策で情報を守れる
- 24時間365日対応のサポートがある
- 柔軟性と拡張性が高く自由度が高い
- 高いパフォーマンスと自動更新で安定した継続利用が可能
それぞれ詳しく解説します。
従量課金制
AWSは従量課金制のため、時間当たりの利用量によって料金が変動します。
余分なコストが発生することがないため、利用方法によっては大幅なコスト削減が可能です。
使い方によって料金が変わるため、試験的に導入したりクラウドサービスの利用コストを極力削減したかったりする場合にもおすすめです。
継続的な値下げがある
AWSは継続的な値下げをおこなっており、サービスが開始された2006年から2024年にかけて80回以上値下げを実施しています。
利用料の値下げは単純にコスト削減になるため、利用者にとっては大きなメリットです。値下げされる一方でサービス内容はアップデートされ続けているため、利用料が下がったからといって利便性が損なわれるということはないのが特徴です。
無料利用期間
AWSには無料利用期間が設けられているため、試験的に導入したり使い方を学習したりしてみたい方はぜひ活用しましょう。
| 期間 | サービスの例 | |
|---|---|---|
| 無料トライアル | ・サービスごとに定められた期間 | ・Amazon SageMaker(2か月) ・Amazon Redshift(2か月) ・Amazon AppStream 2.0(40時間/月) ・Amazon Lightsail(750時間/3か月間) ・Amazon Comprehend Medical(850万文字) ・Amazon Inspector(15日間) ・Amazon Macie(30日間) ・Amazon QuickSight(30日間) ・Amazon GurdDuty(30日間)など |
| 12か月無料枠 | ・アカウント作成から1年間 ・サービスごとに定められた時間/月 | ・Amazon EC2(750時間/月) ・Amazon S3(5GB) ・Amazon RDS(750時間/月) ・Amazon OpenSearch Service(750時間/月) ・Amazon Cloud Directory(1GB/月) ・Amazon Connect(90分/月) ・Amazon EFS(5GB) ・Amazon Elastic Block Storage(30GB) ・Amazon API Gateway(100万/月のAPIコール受信)など |
| 無期限無料枠 | ・サービスごとに定められた期間 ・ストレージや個数など無料になる単位はサービスによって異なる | ・Amazon DynamoDB(25GB) ・AWS Lambda(100万/月リクエスト) ・Amazon CodeWhisperer(無制限) ・Amazon SNS(100万発行) ・Amazon CloudWatch(10カスタムメトリクス) ・Amazon CloudFront(1TB) ・Amazon Cognito(5万MAU/月) ・Amazon Glacir(10GB) ・Amazon Macie(30日間) など |
無料で利用できる内容は時間や容量などサービスによって異なり、試してみたい機能がある場合に活用できる他、少量のみを利用したい場合にもおすすめです。
各サービスの無料利用期間を活用する場合は、それぞれの詳細ページで確認してください。
グローバル展開
世界中約50の地域からサーバーの設置場所を選択できるAWSなら、日本にいてもグローバルなサービス展開が可能です。
システム展開を国内だけでなくグローバルにと考えている場合、AWSを利用すると良いでしょう。
運用保守サポート
AWSでは、情報システムの運用保守についてマネージドサービスが提供されています。
マネージドサービスはサーバー管理に必要な回線、ハードウェア、OSの初期設定、ミドルウェア(※)監視などの作業をAWSが管理してくれるサービスで、利用者の負担を大きく減らしてくれます。
マネージドサービスによって、情報システムの担当者はシステム開発や改善業務に時間と労力を割けるため、生産性向上などのメリットに繋がるでしょう。
※ミドルウェアとは、コンピュータを構成する要素の1つでOSとアプリケーションの中間に存在するソフトウェアのこと
こまめなアップデート
AWSはこまめなアップデートをおこなっており、常に最新の機能を実装し続けています。
利用者のニーズを常に考え、分析し、開発をおこなっているため、利用者が抱える問題を解決へ導いてくれます。また、活用方法によっては新たなビジネスチャンスに繋がることも期待できます。
AWSの機能が拡張されることで、利用者はあらゆる業務を遂行しやすくなるでしょう。
高水準のセキュリティ
AWSにはAmazonのECサイトと同様の高いセキュリティ対策が導入されており、安全性が高いという特徴があります。
また、セキュリティ対策は常に最新のものへ更新されているため、外部からの攻撃や情報漏洩のリスクを抑えられることは大きなメリットです。
またAWSは世界各地にデータセンターを設置しており、データ障害が発生した場合はデータが別エリアのセンターに移動するため、きちんと保護されます。
障害や災害の発生時にデータが確実に守られるため、安心して利用できます。
充実したサポート
AWSは、クラウドサービスを初めて利用する場合でも安心して利用できるように充実したサポート体制を整えています。
AWSの設計や構築をサポートするプランがあり、24時間365日、電話、メール、お問い合わせフォームから利用できます。
サポート体制が整っていることで、クラウドサービスを利用したことがない方やAWSについて詳しくない方も安心して利用を開始できます。
高い自由度
200を超える機能があるAWSでは、利用者それぞれの要望に合わせたサービスの組み合わせや活用が可能です。
例えば、営業時間外のサーバー稼働数を減らしつつ、突発的なアクセス増加があった場合には容量を増加するなど、必要に応じたカスタマイズができます。
AWSは柔軟性や拡張性に優れているため、機能の追加や停止を簡単かつ手軽におこなえるクラウドサービスと言えるでしょう。
安定性
AWSは高いパフォーマンスを安定的に供給するため、利用者に最も近い場所にあるデータセンターからサービスを提供する仕組みになっています。
また定期的な自動アップデートもおこなわれており常に最新の状態が維持されているため、利用者が自分で更新や管理をする必要がありません。
ソフトウェアやハードウェアの管理、サーバーの運営がなくなると、コスト削減や生産性向上といったメリットがあります。
AWSの料金体系を理解しよう
AWSの料金体系は「従量課金制」が基本で、利用した分だけ料金を支払う仕組みです。大きなメリットは、初期投資が不要で必要なときに必要な分だけ使える柔軟さです。例えば学期末のアクセス集中や一時的な研究利用にも対応でき、コストを最小限に抑えられます。また、サービスを使わなければ料金は発生しないため、学習や試験的な利用にも適しています。一方でデメリットは、利用状況を把握せずに使い続けると想定外の料金が発生する可能性がある点です。特に長期間利用する場合や常時稼働が必要な場合は、従量課金制より定額プランやリザーブドインスタンスを選んだほうが割安になることもあります。従量課金制は小規模利用や短期間の利用に向いており、計画的に使えば効率的なコスト管理が可能です。
無料枠を活用し見積もりを取ると安心
AWSの無料枠は、Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon S3などで利用でき、一定の容量や時間を1年間無料で試せます。無料枠を活用すれば、費用をかけずにさまざまな構成や運用パターンを試せ、必要なリソース量を見積もることができます。また、予期せぬ請求を防ぐアラート機能を設定すれば、安心して学習や検証に取り組めます。
【一覧表】AWSが提供する主要サービス9種

AWSには多種多様なサービスがありますが、多くのユーザーが利用している主要なサービスを以下にまとめました。
| サービス名 | できること | 想定シーン |
|---|---|---|
| Amazon EC2 | Webサイトや各種サーバーの運用 | ・AWS上でのファイルサーバーやADサーバーなどを利用したい ・Webサイトをクラウド上で構築したい |
| Amazon S3 | データの保管とバックアップ | ・AWS上でデータを保管したい ・AWS上でデータのバックアップを取りたい |
| Amazon RDS | マネージドサービス(アップデートやバックアップなどの保守業務) | ・AWS上でデータベースを使いたい ・保守業務を削減したい |
| Amazon Route53(アマゾンルート53) | DNS(ドメインネームサービス)(サービスのドメインを登録することでWebサイトやメールサービスと関連付ける) | ・AWS上で新規ドメインを取得したい ・既存ドメインを持ち込みたい |
| Elastic Load Balancing(エラスティックロードバランシング) | Webサービスに発生する負荷を分散させる | ・AWS上でWebサービスを実装したい ・Webサービス利用時の負荷を分散させたい |
| Amazon WorkSpaces(アマゾンワークスペース) | 仮想デスクトップを立ち上げ利用する | ・社内でもリモートでも同一の作業環境を利用したい ・MacやLinuxを使っているが稀にWindowsアプリを利用する |
| AWS Direct Connect(アマゾンダイレクトコネクト) | インターネットを介さずにAWSサービスに接続し利用する | ・社内システムをAWSに導入したい ・オンプレミスサーバーからサーバーへデータを素早く移動させたい ・セキュリティの高い接続方式を導入したい |
| Amazon Cloud Front(アマゾンクラウドフロント) | コンテンツ配信 | ・コンテンツファイルをWebサイトで配信したい |
| Amazon EMR | 大量のデータを高速で処理する | ・ビッグデータ分析をしたい ・機械学習をしたい |
利用シーンによって適したサービスを組み合わせることで、より効率的にシステムの開発、運用、保守、展開をおこなうことができます。
AWSにはデメリットもあるため要チェック

機能も魅力も盛りだくさんなAWSですが、利用に際してデメリットも存在します。
- アカウント登録にはクレジットカードが必要
- AWSのダウンタイムにはシステムが一時停止される
ここでは、2つの大きなデメリットについて解説します。
アカウント登録にはクレジットカードが必要
AWSへの新規アカウント登録のときは、クレジットカードの登録が必要です。個人での利用では特に大きな問題ではないですが、企業が利用する場合は手間がかかることがあります。
企業がAWSを利用する場合は、事前にコーポレートカードやビジネスカードを用意しておくと良いでしょう。
AWSのメンテナンス時にはシステムが一時停止される
AWSでシステムメンテナンスなどがおこなわれると、システムが一時的に停止し利用できなくなることがあります。
事前にスケジュールが通知されるものの、その間は業務が停滞してしまうリスクがあるため、AWSのダウンタイムに合わせた業務計画を立てる必要があります。
特に一般公開するWebサイトなどを運営する場合、ユーザーに向けた通知なども欠かさないことが大切です。
AWSとMicrosoft Azure・Google Cloudに違いはある?

AWSに並んで、人気のあるクラウドサービスに「Microsoft Azure(マイクロソフトアジュール)」と「Google Cloud(グーグルクラウド)」があります。
3つのサービスには、以下のような違いがあります。
| サービス | Amazon Web Service(AWS) | Microsoft Azure(Azure) | Google Cloud(GCP) |
| 提供企業 | Amazon | Microsoft | |
| 料金 | 従量課金制 | 従量課金制 | 従量課金制 |
| 特徴 | ・最新技術を導入している ・他のクラウドサービスにはない独自のサービスが多数ある | ・Microsoft製品との互換性があり親和性が高い | ・機械学習やデータ分析などの基盤が強い |
| サポート | ・電話 ・メール ・チャット | ・電話 ・メール ・コミュニティ | ・電話 ・メール |
| 弱点 | サービス設定の難易度が高め | インターネット上にトラブル解決のための情報が少ない | 日本語情報が少ない |
以下では、Microsoft AzureとGoogle Cloudの概要を紹介します。
Microsoft Azure(マイクロソフトアジュール)の概要
Microsoft Azureは、Windowsを手がけるMicrosoft社が提供しているクラウドサービスです。
Windowsをベースにしているサービスで、Microsoft製品との親和性が高いことが大きな特徴として挙げられます。
また政府機関も利用するほど堅牢なセキュリティを保持していることも特徴で、重要なデータを保管するのにもおすすめです。
Google Cloud(グーグルクラウド)の概要
Google Cloudは、Googleが提供しているクラウドサービスです。
検索処理、広告の最適化といったGoogleの自社サービスによって蓄積された知識や技術を活かしたクラウドサービスであり、独自のサービスが数多く用意されています。
特に機械学習(AI)やデータ分析に強みをもつため、ビッグデータ分析や機械学習などに活用したい場合におすすめです。
AWSなどのパブリッククラウドサービスを選ぶ際のポイント

AWSを始めとするクラウドサービスを選ぶときは、以下の2点をきちんとチェックしましょう。
- 自社に必要な機能を備えているか?
- サポート体制は充実しているか?
それぞれ詳しく解説します。
必要な機能があるか
クラウドサービスを選ぶときは、自社に必要な機能が備わっているものを選びましょう。
クラウドサービスはそれぞれ提供しているサービスや強みも異なります。ただ有名だから、おすすめされたから、といった理由でクラウドサービスを選んでしまうと、使い始めてから自社の運用方法とマッチしないことに気づくというケースに陥ってしまうことがあります。
クラウドサービスごとの機能、提供サービス、強み、弱みを事前にチェックしたり、無料利用期間で試験的に利用したりしてから選びましょう。
どのようなサポートがあるか
サポート体制は、クラウドサービスを選ぶときの重要なポイントです。
サポートの対応時間、サポート内容、ヘルプページの有無、メールやライブチャットといったサポートに関する充実度については事前にチェックしておくと良いでしょう。
後々困りごとができたときなど、安心して頼れるサポートがあるクラウドサービスを選ぶのがおすすめです。
AWSのセキュリティ性を高めるポイントとは?

AWSのセキュリティ性をより高め、自社のデータやシステムを安全に運用、管理するためには以下の2つのポイントをおさえることが重要です。
- 閉域ネットワークを利用して接続を制限する
- AWSのセキュリティを理解したうえで必要な対策をおこなう
それぞれ詳しく解説します。
閉域ネットワークを使う
クラウドへ接続するときは閉域ネットワークを利用し、接続を制限してセキュリティの安全性を高めましょう。
閉域ネットワークとは、インターネットと分離されたネットワークのことを指し、限られたユーザーや拠点からしか接続できないことが特徴です。
クラウドへの接続方法はさまざまですが、自社のデータをより高いセキュリティで守るなら閉域ネットワークの利用がおすすめです。
AWSのセキュリティを理解する
AWSにはあらかじめ定められたセキュリティがあるため、AWSのセキュリティ範囲について理解したうえで必要な対策をおこなう必要があります。
サービスごとにセキュリティの範囲が異なるため、それぞれのサービスに必要なセキュリティ対策をきちんと考えてから利用しましょう。
またAWSのセキュリティ対策の内容はアップデートされることがあるため、常に最新のセキュリティが実装されていることを確認しておくことも大切です。
AWSを導入した企業事例6選

実際にAWSを導入した企業の事例を、6つピックアップして紹介します。
- ファイルサーバーのクラウド化|株式会社医歯薬ネット
- リアルタイムの監視・解析サービスの開発|株式会社イー・コミュニケーションズ
- 社内環境のDX化推進|資産科学研究所
- 自然災害や事故などに備えた対策|森永製菓株式会社
- 大規模データのクラウド移行|全日本空輸株式会社(ANA)
- 膨大なアクセス数に対する対策|株式会社日本経済新聞社
それぞれ詳しく紹介します。
AWSの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ファイルサーバーのクラウド化|株式会社医歯薬ネット
ファイルサーバーのクラウド化にAWSを活用した事例です。
株式会社医歯薬ネットでは、クラウド導入前には情報システム基盤の不安定さやシステム運用の稼働削減などの課題がありましたが、AWSを使うことで情報システムの担当者を立てずにファイルサーバーをクラウド化させることに成功しています。
クラウド化にAWSを活用することで情報システム担当者の稼働を削減したり、ネットワークを見直してトラブル発生時の対策にかかる負担を軽減したりすることができました。
リアルタイムの監視・解析サービスの開発|株式会社イー・コミュニケーションズ
リアルタイムの監視・解析サービスの開発の成功事例です。AWSの俊敏性が活き、開発からリリースまで短期間で進めることができました。
資格や組織内にまつわる試験をおこなう株式会社イー・コミュニケーションズでは、クラウドAIで動画を自動で監視・解析することで厳正な試験を実現するサービスの開発とリリースに成功しています。
自社サービスの価値アップや競争力強化に繋がった事例として参考になるでしょう。
社内環境のDX化推進|資産科学研究所
AWSを活用した社内環境のDX化推進に成功した事例です。
社外からのサーバーアクセスを可能にして業務を効率化したい、情報セキュリティを強化したい、在宅ワークを取り入れた労働環境の整備をしたいといった課題を抱えていた資産科学研究所では、AWSによって社内環境のDX化推進を成功させました。
ファイルサーバーをクラウド化することで、時間や場所にとらわれないデータ管理を取り入れつつ高いレベルのセキュリティでデータを保管できるため、生産性向上やリスク管理に成功する結果となっています。
自然災害や事故などに備えた対策|森永製菓株式会社
全システムをAWSに移行し、自然災害や事故などの不測の事態に備えることに成功した事例です。
森永製菓株式会社では2017年頃からクラウドの導入を本格化しており、最も安定性があると判断したAWSを利用することに決定したと言います。
自然災害や事故など不測の事態に備え、すべてのデータをクラウドへ移行して安全に管理しています。
大規模データのクラウド移行|全日本空輸株式会社(ANA)
大規模データをクラウドへ移行して管理できるようにした事例です。
全日本空輸株式会社(ANA)は大手航空会社として知られており、航空券の予約、発見、運航実績など膨大なデータを取り扱っています。
クラウドへのデータ移行には慎重になっていたところ、AWSの豊富な導入実績や高いセキュリティが決定打となり、無事に膨大なデータのクラウド移行に成功しました。
20年以上蓄積してきたデータをオンプレミス環境からスムーズにクラウドへ移行させ、現在は安全かつ安定的にデータを管理しています。
膨大なアクセス数に対する対策|株式会社日本経済新聞社
日経電子版などを運営する株式会社日本経済新聞社では、AWSによってサーバーの管理の見直しをおこないました。
日経電子版への膨大なアクセス数とそれに伴うサーバー管理をAWSに移行することで、負荷の分散装置をしたり負荷に応じた柔軟な対応をしたりするといった対策を実現しています。
AWS認定資格について
AWS認定資格は、Amazon Web Services に関する知識や技術力を公式に証明するための資格で、クラウド分野に携わる人材のスキルの可視化やキャリアアップに大きく役立ちます。資格は4つのレベルに分かれており、クラウドの基礎を問う初心者向けの「Foundational」、実務レベルでの設計や運用を対象とした「Associate」、高度な設計力や運用スキルを求められる「Professional」、さらにセキュリティやデータ分析など特定領域に特化した「Specialty」があります。代表的な資格には「AWS Certified Cloud Practitioner(Foundational)」「AWS Certified Solutions Architect – Associate」「AWS Certified Solutions Architect – Professional」「AWS Certified Security – Specialty」などが挙げられます。難易度はFoundationalが比較的易しく、ProfessionalやSpecialtyは深い知識と実務経験が不可欠です。合格率は非公開ですが、レベルが上がるほど低い傾向にあるとされます。学習には公式トレーニングや模擬試験に加え、ハンズオンによる実践的演習を組み合わせることで、効率的かつ確実に知識を習得できます。
AWS認定資格を取得するメリット
AWS認定資格を取得するメリットは、クラウドに関する知識やスキルを客観的に証明できることです。これにより、業務での信頼性が向上し、プロジェクト参画や昇進、転職活動でも有利になります。また、資格取得の過程で最新のAWSサービスや設計手法を学べるため、実務での応用力も高まります。さらに、企業からの評価やキャリア形成だけでなく、AWSコミュニティやネットワークへの参加機会が増え、情報交換やスキル向上にも役立ちます。資格は自分の知識の到達点を確認する指標にもなるため、学習のモチベーション維持にもつながります。
AWS認定資格の勉強方法
AWS認定資格の勉強方法には、独学、通信講座、スクール受講などがあります。独学は公式ドキュメントや書籍、模擬試験を活用でき、費用を抑えつつ自分のペースで学習可能です。通信講座は動画教材やオンライン演習を使って体系的に学べ、場所や時間を選ばず効率的に進められます。スクール受講は講師から直接指導を受けられ、疑問点を即解決できるため理解が深まりやすく、模擬試験やハンズオン演習も充実しています。どの方法でも、実務経験やハンズオンでの演習を組み合わせることで、理解を定着させ、合格率を高めることができます。
クラウドなどの情報知識を学ぶなら、開志創造大学 情報デザイン学部がおすすめ
開志創造大学 情報デザイン学部は完全オンラインで大学を卒業できる通信制の学部です。いつでもどこでも学べるので、自分の都合に合わせて自由に授業を受けられるのが特長です。
情報デザイン学部では、今回の記事で解説したAWSのようなクラウドサービスやソフトウェア・ハードウェアなどの情報に関する知識や技術を学ぶことができます。
これから先の時代、今まで以上に情報に関する知識や、最先端のIT・AIの知識などが求められる世の中になっていきます。
そんな知識や技術を「年間授業料25万円」「1回15分の授業動画」の情報デザイン学部で身につけませんか?
まとめ

Amazon Web Service(アマゾンウェブサービス)は、「AWS」の略称で知られるAmazonが提供するクラウドサービスです。
AWSには200を超えるサービスが備わっており、必要に応じてサービスを組み合わせて応用的に運用することができるのが特徴です。
また、世界最大のECサイトであるAmazonの運営で蓄積されたハイレベルなセキュリティを導入しており、安全かつ安定的な利用が可能になっています。
AWSが持つ拡張性と俊敏性はビジネスにおいても良い影響を及ぼし、導入することで多くの企業が生産性向上や業務の効率化、新たなビジネスチャンスの獲得といった事例を実現しています。
AWSを始めとするクラウドサービスにはMicrosoft Azure(マイクロソフトアジュール)やGoogle Cloud(グーグルクラウド)などがありますが、それぞれが持つ特徴、強み、弱み、サポートなどは異なるため、自社の運営方法に合ったサービスを選ぶことが大切です。
クラウドサービスを導入し、業務効率化や新サービスの開発などの成功を目指しましょう!