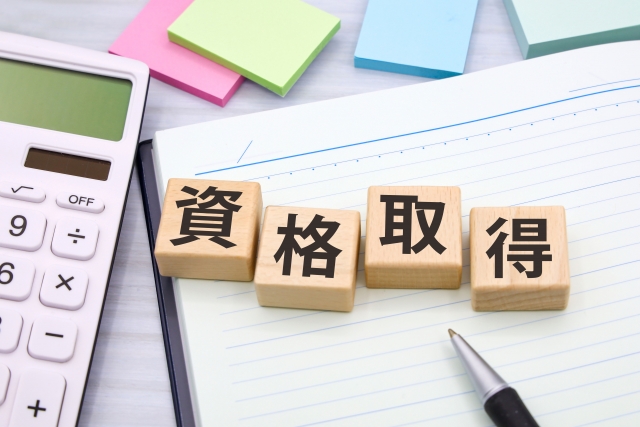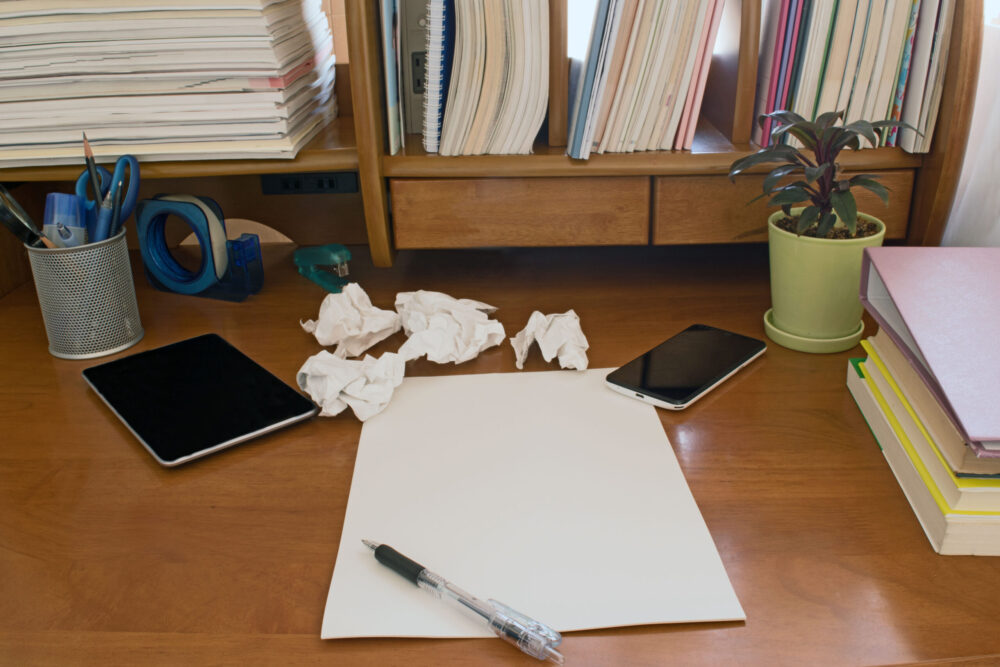AIエージェントとは?特徴・生成AIとの違い・活用例まで解説!
AIの技術進化により、これまで人の指示をもとに動いていたAIが、自ら目標を理解し、最適な行動を選ぶ「AIエージェント」へと発展しています。
業務の自動化や意思決定支援など、ビジネスのあらゆる領域で注目が高まるAIエージェントについて、本記事では、その基本的な仕組みから特徴、生成AIとの違いや、活用例までわかりやすく解説します。
AIエージェントについて興味がある方はぜひ最後までご覧ください。
目次
AIエージェントとは何?

AIエージェントとは、与えられた目標を達成するために自律的に考え、行動するAIシステムです。
従来のAIは、人間が具体的な指示や条件を与えることで動作する仕組みでした。一方でAIエージェントは、人の細かな指示を待たずに、AI自身が状況を理解し、与えられた目標を達成するために最適な計画を立ててタスクを実行します。
これにより、作業の効率化や意思決定の迅速化が可能になります。
AIエージェントと生成AIの違いは?

生成AIは、ユーザーから与えられた指示(プロンプト)に基づいて、テキスト・画像・音声・動画などのコンテンツを生成するAI技術を指します。主に「与えられた入力に応答する」形式で動作し、指示がなければ自発的に行動することはありません。
一方、AIエージェントは、与えられた目標(ゴール)を達成するために自律的に考え、行動するシステムです。膨大なデータや外部ツールを活用しながら、テキスト・画像・音声などさまざまな情報を、それぞれに合った解析方法で分析し、その結果をもとに最適な手段を選択してタスクを実行します。
生成AIが「創り出す力」に優れているのに対し、AIエージェントは「考えて行動する力」に優れています。
つまり、AIエージェントは生成AIを活用しながら、より高度に自律的な判断とタスク実行を行う存在といえます。
AIエージェントの仕組みとは
AIエージェントは、「タスクを作成・管理する」「最適なタスクの実行方法を考える」「決定した方法でタスクを実行する」というサイクルをAI自身が柔軟に繰り返しながら、目標の達成に向けて自律的に行動する仕組みになっています。
まず「タスクを作成・管理する」段階では、与えられた目標を達成するために必要な作業を、複数の小さなタスクに分解します。
たとえば「新製品のマーケティング戦略を立てる」という目標であれば、市場動向の調査、競合製品の分析、顧客ニーズの把握などに細分化して整理・管理します。
次の「最適なタスクの実行方法を考える」段階では、分解された各タスクをどのように進めるのが最も効果的かをAIが自ら判断します。
たとえば競合分析では、公式サイト、業界レポート、SNSの口コミデータなど複数の情報源を照合する方法が最適だとAIが判断するといった行動がこれにあたります。
そして「決定した方法でタスクを実行する」段階では、導き出した方法で実際にタスクを実行し、さらにその結果をもとにして次の行動を調整していきます。
この「タスクを作成・管理する」「最適な実行方法を考える」「決定した方法でタスクを実行する」のサイクルをAI自身が繰り返すことで、環境や情報の変化にも柔軟に対応ながら継続的に活動し、自律的に目標達成までたどり着くことが出来ます。
AIエージェントの6つの種類

AIエージェントには、機能や目的に応じてさまざまな種類があります。以下では、それぞれの特徴や仕組みを順番に解説し、実生活や仕事でどのように活用できるかもご紹介します。
①反応型
最も基本的なタイプのAIエージェントです。あらかじめ設定されたルールや条件に従って動作し、外部からの入力やAIが置かれている環境の変化に応じて、決められた反応を返すように設計されています。
例えば、特定の質問に対して決まった答えを返すチャットボットや、簡単な計算・データ整理などを自動で行うプログラムがその代表例です。
自分で考えたり学習したりすることはできませんが、決められた処理を正確に繰り返すことに優れているため、単純な業務や定型的な作業を自動化する場面で効果を発揮します。
②目標ベース型
設定された目標を達成するために、最適な行動を自律的に選択するタイプのAIエージェントです。
与えられた目標に向けて複数の選択肢を比較し、条件や制約を考慮しながら、最も効果的な方法を判断します。
たとえばスケジュール調整の場面では、参加者全員の予定を分析し、全員が参加できる最適な日時を自動で提案します。
このように目標達成に向けて数多くの選択肢を比較しながら段階的に判断を重ねることで、人間の負担を減らし、業務の効率化や意思決定の質の向上に貢献します。
③モデルベース型
モデルベース型エージェントは、環境の状態を内部モデルとして保持し、その変化に応じて最適な行動を選択するAIです。
たとえば工場の生産ラインにおいては、センサーデータから設備や生産状況をリアルタイムで把握し、効率や安全性を考慮した最適な運転条件を自動で調整します。
このように、環境の変化を予測しながら行動するため、単純な反応型AIよりも柔軟で効率的な制御や意思決定が可能です。
④効用ベース型
効用ベース型AIエージェントは、単に目標を達成するだけでなく、行動の結果として得られる「成果」や「満足度」を最大限に高めることを重視するタイプのAIです。
たとえば、金融市場で取引を行うシステムに利用する場合、利益の大きさだけでなく、リスクやコスト、市場の動向など複数の要素を総合的に評価し、最も効率的で有利な取引方法を自ら考えて選択します。
さらに、状況や条件が変化しても柔軟に判断できるため、単純なルール通りの行動では対応できない複雑な問題に対しても、より的確で最適な意思決定を行うことが可能です。
⑤学習型
これまでに蓄積された経験やデータをもとに改善・学習を行い、時間の経過とともに性能を高めるタイプのAIです。
過去の行動結果や外部から得た情報を学習して次の判断や行動に反映させることで、より的確に対応できるようになります。
たとえばカスタマーサービスでは、問い合わせ内容や対応履歴を学習することで、より正確で迅速な回答を提供できます。
継続的な学習により、顧客の傾向や新たな課題にも柔軟に対応ができます。
⑥階層型
階層型AIエージェントは、複数のAIが下位層・上位層に分かれた階層構造の中で役割を分担しながら協力して動作する仕組みをもつ高度なAIシステムです。
下位層では、さまざまなタイプのAIエージェントがそれぞれの担当タスクをお互いに協力しあいながら実行します。
上位層では、下位層から集まった情報や結果をもとに全体の目標に沿って判断や指示・フィードバック、最終的な意思決定を行います。
たとえば工場の製造ラインでは、下位エージェントが部品の準備・組み立て・搬送などに関わる作業をそれぞれが分担し担当、上位エージェントが下位層の情報をもとに全体の進行状況を監視しながら、効率よく作業が進むように最適化します。
また、物流システムでは、配送計画や在庫管理などの下位層から集めた情報を上位層が整理・調整することで、ミスや遅れを防ぎ、より安定した運用を実現できます。
AIエージェントが今求められている理由

AIエージェントが今求められている理由の背景には、労働人口の減少とデジタル化・グローバル化の急速な加速によるビジネス環境の複雑化といった「社会的な要因」と、近年のAI技術の進化や一般化といった「技術的な要因」が挙げられます。以下で詳しく見ていきましょう。
LLM(大規模言語モデル)の進化
従来のLLM(大規模言語モデル)は、回答の正確さや処理速度の面で課題がありAIエージェントの実際の業務への活用は不安視されていました。
しかし近年、モデルの構造や学習方法の改良によって性能が大幅に向上し、AIエージェントの実用化を後押ししています。具体的には、次のような進化が見られます。
- 複雑な問題を段階的に整理し、「まず考えること」「次に判断すべきこと」といった形で、順序立てて考える能力が強化され、回答の精度が向上。
- 自分の内部データベースに加え、外部の信頼できる情報源をリアルタイムで参照する能力が向上。より根拠のある結論を導けるようになった。
- AI自身が過去の推論の過程を振り返り、誤りを修正して精度を高める仕組みが進歩。
- 専用AIチップの性能が飛躍的に高まり、複雑な処理の短時間での実行を実現。
- AIがパソコン操作を行う「Computer Use」機能や、テキスト・画像・音声など複数の情報を組み合わせて判断し複雑な課題に対応可能な技術「マルチモーダルAI」の発展により、より人間に近い感覚で状況を把握し、的確な計画や行動を取れるようになった。
こうした技術的進化が、従来のLLMの課題を解消しAIエージェントでのより高度で実践的なタスクの実行を実現可能にしました。
AIの一般への普及に伴いエージェント型AIの需要が拡大
2022年のOpenAIによるChatGPTの公開をきっかけに、AI技術の普及が加速しました。2024年後半にはMicrosoftの「Copilot PC」やGoogleの「Gemini2.0」といったAIが登場し、一般ユーザーの間でもAIの活用が広がっています。
2025年に発表されたOpenAIの「Operator」では、ユーザーの指示をもとにAIがWebブラウザを操作して情報を収集・整理・分析し、ComputerUse機能を利用してタスクの完了までこなすようになりました。
この機能は企業だけでなく個人の業務や日常生活でも活用されており、現在の「自律的に作業を行うAIエージェント」の実現に大きく貢献しています。
こうしてAIは単なる補助役から、自ら考えて行動し、意思決定や業務効率化に貢献する存在へ進化しており、AIエージェントの需要拡大につながっています。
技術競争に伴い技術革新が加速しAIエージェントの実用化が現現実に
従来のチャット型AIはユーザーの指示に応答するだけで、自律的に複雑な作業を行うことはできず、業務を完全に自動化するには限界がありました。
しかし、2024年10月にAnthropicが公開した「Claude 3.5 Sonnet」では、PC画面を認識して操作までこなす「ComputerUse」機能が搭載され、AIがより自律的に作業を実行できるようになりました。
さらに、2024年12月にはGoogleからモーダルAI(テキスト・画像・音声を組み合わせて、より人間の五感に近いイメージで処理を実行するAI)として「Gemini2.0」が公開され、AIエージェントの実用化を大きく後押ししました。
その後もクラウド技術をメインにビジネスを展開する企業を中心に、AIエージェント技術の競争が活発となり、OpenAIの「Operator」やSalesforceの「Agentforce2.0」など2025年現在も優れた機能をもつAIが次々と登場しています。
各社は従来の「対話型AI」から「自律的に作業を実行するAIエージェント」へ技術開発の方向をシフトしており、こうした技術競争と急速に進む技術革新がAIによる、より高度なタスクの実現を可能にしAIエージェントの業務への実用化を促進しています。
労働不足によって、業務自動化の需要が拡大
少子高齢化の影響によって、人手不足はあらゆる業界で深刻な課題となっています。労働人口の拡大には限界があり、将来的には慢性的な人手不足が続くことが懸念されています。
こうした中で注目を集めているのがAIエージェントです。AIエージェントは、人の代わりに自律的にタスクをこなせる存在であり、データ管理や事務処理などの定型業務だけでなく、顧客対応や情報分析といったより高度で複雑な業務にも対応できます。
これらの特性により、AIエージェントは深刻化する労働力不足の中で業務の自動化を推進し、人手不足の解消とともに、企業の生産性を安定的に維持・向上させる手段として期待されています。
AIエージェントの3つのメリット

AIエージェントには「業務をAIエージェントが自律的に行うことによる負担軽減」、「迅速で的確な意思決定の実現」、「既存の業務システムと柔軟に連携が可能」という3つのメリットがあります。以下でそれぞれについて具体的にご紹介します。
業務をAIエージェントが自律的に行うことによる負担軽減
AIエージェントは、人が細かく指示を出さなくても、自ら考えて仕事を進めることができます。たとえば、データの整理やメール対応、スケジュール調整など、時間のかかる作業を自動で実行することができます。
これにより、社員は事務的な作業の負担を減らしながら、より重要な判断や企画業務に集中できるようになります。また、AIは24時間稼働できるため、人が不在の時間帯でも業務を継続することが可能です。
その結果、作業スピードの向上やミスの減少が期待でき、全体の効率が大きく改善します。AIエージェントの導入で、社員の負担軽減と生産性向上の実現が可能であるというメリットから、現代のビジネス環境において欠かせない存在となりつつあります。
迅速で的確な意思決定の実現
AIエージェントは、単にデータを分析するだけでなく、その結果をもとに最適な行動を自動で選び、実行することができます。
これにより、単に作業を素早くこなすだけでなく、より精度の高い意思決定を実現することが可能になります。
たとえば、過去のデータや結果を活用して最適な判断を下したり、企業内のさまざまな部署に散らばる情報をまとめて分析し、最も効果的な対応策を導き出すことができます。
また、市場の変化や顧客の反応に合わせて、価格設定や広告内容をリアルタイムに調整することも可能です。
このように、AIエージェントは「分析」から「実行」までを一貫して担うことで、経営や事業戦略レベルでの意思決定を支援し、実行可能でより効果的な施策の立案と実施をサポートします。
既存の業務システムと柔軟に連携が可能
AIエージェントは、特定の作業を自動で行うだけでなく、会社全体の仕事の流れに合わせて柔軟に動くことができます。
たとえば、営業に関する業務や注文管理、商品の配送など、これまで別々の部署で行っていた仕事をAIエージェントがまとめて連携・管理することで、必要な情報をすぐに共有でき、チーム全体の連携もスムーズになります。
また、複数のAIエージェントがそれぞれの役割を持ちながら協力することで、会社全体の仕事を自動で整理し、より正確で効率のよい判断や対応ができるようになります。
さらに、新しい仕事の内容や目標が出てきた場合でも、AIが自動的に学習して新しい仕組みに合わせられるのも大きな強みです。
AIエージェントは、ただ仕事を自動でこなすだけでなく、日々の業務を支え、働きやすさや生産性の向上にもつながる存在といえます。
AIエージェントの抱える課題
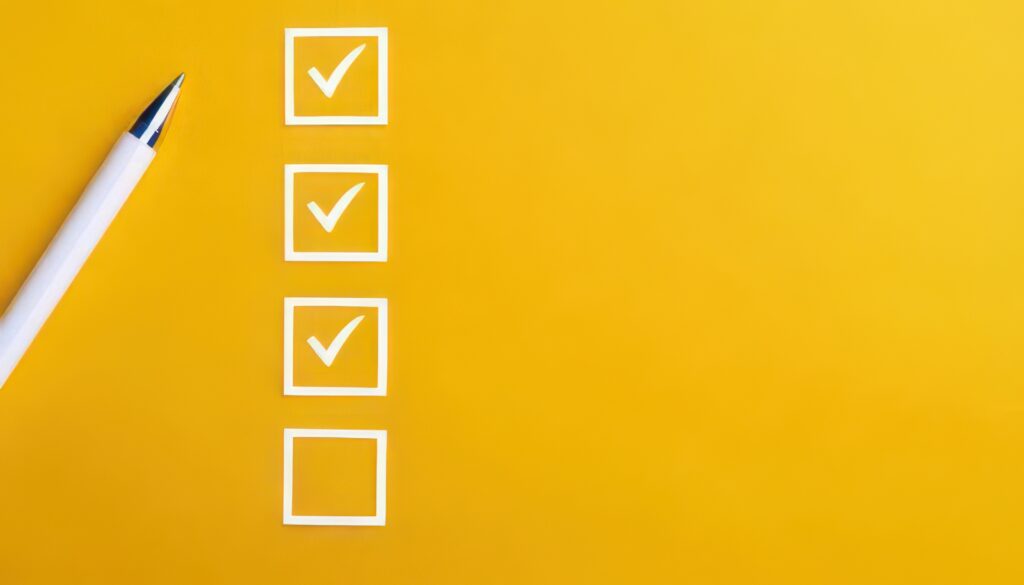
AIエージェントには多くのメリットがありますが、一方でいくつかの重要な課題も存在します。まず、AIは事実と異なる情報を生成してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起きることがあります。
そのため重要な判断を行う際には、人間による最終的な確認が欠かせません。また、AIエージェントは機密情報や個人データを扱うことが多く、セキュリティ対策が非常に重要です。
データの暗号化やアクセス制限など、安全な運用体制を整えることが求められます。さらに、AIがどのような考え方で判断を下したのかが分かりにくい場合、倫理的・法的な問題が生じるおそれもあります。
そのため、責任の所在を明確にし、AIの判断過程の透明性を確保することが重要です。加えて、AIを正しく活用するためには、技術やデータ分析に関する知識を持つ人材の育成も欠かせません。
これらの課題に適切に対応していくことで、AIエージェントの信頼性と価値はより高まり、社会やビジネスの発展に役立てることができます。
AIエージェントの活用例

AIエージェントは、業務の自動化や効率化、データ分析の支援を通じて、担当者の負担を減らし、生産性やサービスの質を向上させます。以下では、こうしたAIの活用例についていくつか紹介していきます。
カスタマーサポート
AIエージェントは、カスタマーサポートの効率化やサービス向上に役立っています。
現在は、チャットボットを使った基本的な問い合わせ対応が中心で、ユーザーの質問に対してLLM(大規模言語モデル)が持つ膨大なテキストデータをもとにAIが回答する仕組みを利用した業務や、問い合わせ内容に応じてどの部署の担当者に振り分けるかを判断する中継業務で活用されています。
これにより業務の自動化やオペレーターの負担軽減、迅速な顧客対応が可能になっています。
今後はAI同士が連携することで、顧客の過去のやり取りや状況を考慮し、より複雑な問い合わせにも対応できるようになると期待されています。
AIエージェントは、単に業務を効率化するだけでなく、顧客一人ひとりに最適化されたサービスの提供も可能にします。
事務業務
事務作業は、AIエージェントの導入によって自動化と効率化が大きく進んでいます。
スケジュールの調整やデータの入力といった毎日のくり返し作業を自動で行い、複数のツールを使い分けながら、AIが自律的に業務を進めることで従業員の仕事をサポートしています。
AIが作成したレポートや資料を人が確認するだけでよくなるため、働く人の負担が大きく減っています。今後は、異なる部署や業種の業務を仲介・調整したり、情報共有を行ったり、特別な対応が必要なケースが発生した場合にも柔軟に対応できるようになるでしょう。
また、アイデアを考えるような企画の仕事でも、AIが下書きを作ってくれることで、人が考える時間を短くしながらより良い成果を出せるようになると期待されています。
営業活動
営業活動でもAIエージェントを導入することで、担当者の負担を大幅に軽減することが可能になります。
今まで人の手で行われていた顧客データの分析や契約管理、提案資料の作成といった作業を自動化することで、営業担当者はより重要な戦略の立案や顧客との信頼関係の構築に時間を割けるようになります。
さらに、複数のAIエージェントが連携して市場動向や顧客の反応をリアルタイムに把握することで、AIが最適な営業戦略や提案内容を自律的に調整し提案できるようになることも見込まれています。
こうした仕組みによって、営業活動全体の効率化が進み、成果を最大限に引き出せるようになることで、企業の収益向上にも大きく貢献することが期待されています。
教育現場
教育現場においても、少子高齢化による教員不足が進む中、教員の業務負担を軽減するためにAIの導入が広がっています。
AIは、生徒一人ひとりの得意・不得意や理解度、学習履歴を分析し、最適な教材や課題を提案して個別学習をサポートします。
また、テストの採点や教材作成、出欠管理など、これまで教員が多くの時間を費やしていた作業を自動化することも可能です。こうした仕組みにより、教員は生徒との対話や進路指導といった、人にしかできない教育活動により多くの時間を使えるようになります。
また、生徒が自分のペースで無理なく学べるようになることで、勉強への意欲が高まり、得意分野をさらに伸ばせるようになることも期待されています。
AIエージェントについてよくある質問

AIエージェントとAIアシスタントの違いは何ですか?
AIエージェントは、与えられた目標(ゴール)を達成するために自律的に考え、行動するシステムで、必要な計画や実行も自分で行います。
一方で、AIアシスタントはユーザーから与えられた指示(プロンプト)に従い、情報提供や操作の補助などを行う支援型のAIです。
AIエージェントのデメリットは?
AIエージェントは自律的に考え、行動できる反面、間違った情報を生成するリスクがあるため、人間による確認が必要になります。
また、個人情報を扱う場合は、情報漏えいや不正アクセスなどのセキュリティ面での危険も伴うといったデメリットがあります。
AIについて学ぶなら、開志創造大学
開志創造大学 情報デザイン学部は、2026年4月に開設する新しい通信教育課程の学部です。完全オンラインで学べるため、一度も通学することなく大学を卒業することができ、「学士(情報学)」の取得が可能です。
年間授業料は25万円と、学びやすい価格設定で、授業は1回15分のオンデマンド授業(事前収録の動画)のため、いつでもどこでも学修を進めることができます。
ITやデジタル技術を学ぶことは、現代のビジネスの現場においてとても価値があります。開志創造大学 情報デザイン学部では、AI・機械学習の基礎から応用までを、スクーリング一切なしの「完全オンライン」の柔軟な学修スタイルで、一人ひとりの生活リズムに合わせて学ぶことができます。
AIやITの知識について深く学びたい方は、開志創造大学情報デザイン学部がおすすめです。ご興味のある方は、ぜひ学部の詳細ページをご覧ください!
まとめ
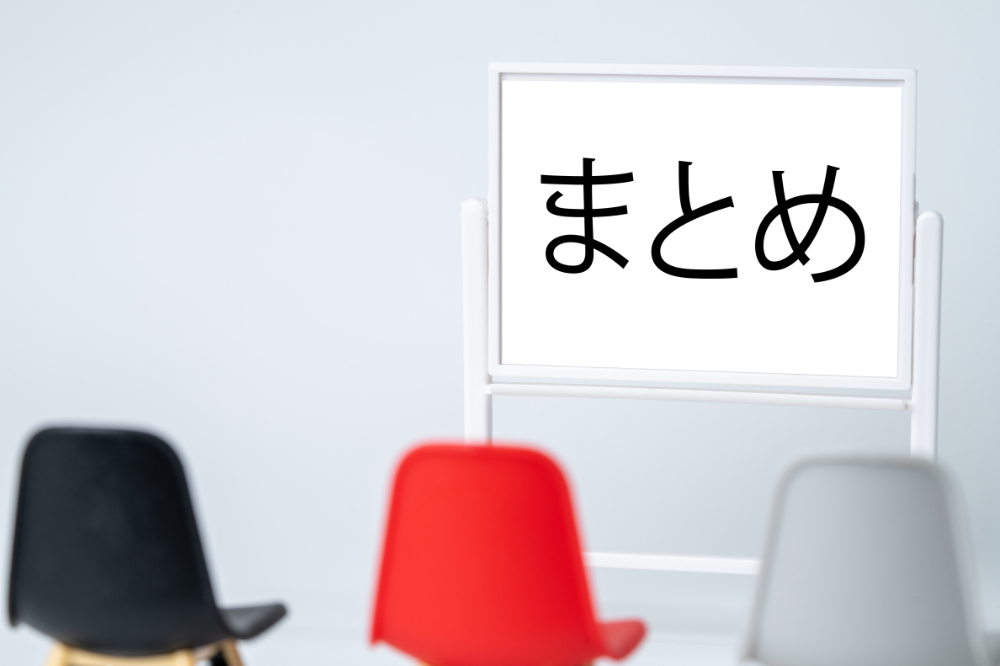
AIエージェントは、「自分で状況を判断し、最適な行動を選べる自律型のAI」です。ビジネスや教育、医療などさまざまな分野で活用され、仕事の効率化や迅速化、顧客対応、学習サポート、データ整理など幅広い分野で役立っています。
一方で、間違った情報を生成してしまう可能性や、個人情報を扱う上でのセキュリティ対策の問題、AIの使い方が社会的に適切かどうかといった、いくつかの課題もあります。こうした課題を理解したうえで適切に活用することでAIの信頼性を高め、人とAIが協力して働ける環境を作ることが大切です。
こうした取り組みによって、AIが単なる自動化ツールとどまらず、新しいアイデアを生み出したり、今までにない方法で問題を解決したりできる社会の実現へとつながります。
AIエージェントはそういった社会の実現へ貢献できる存在として、ますます期待されています。