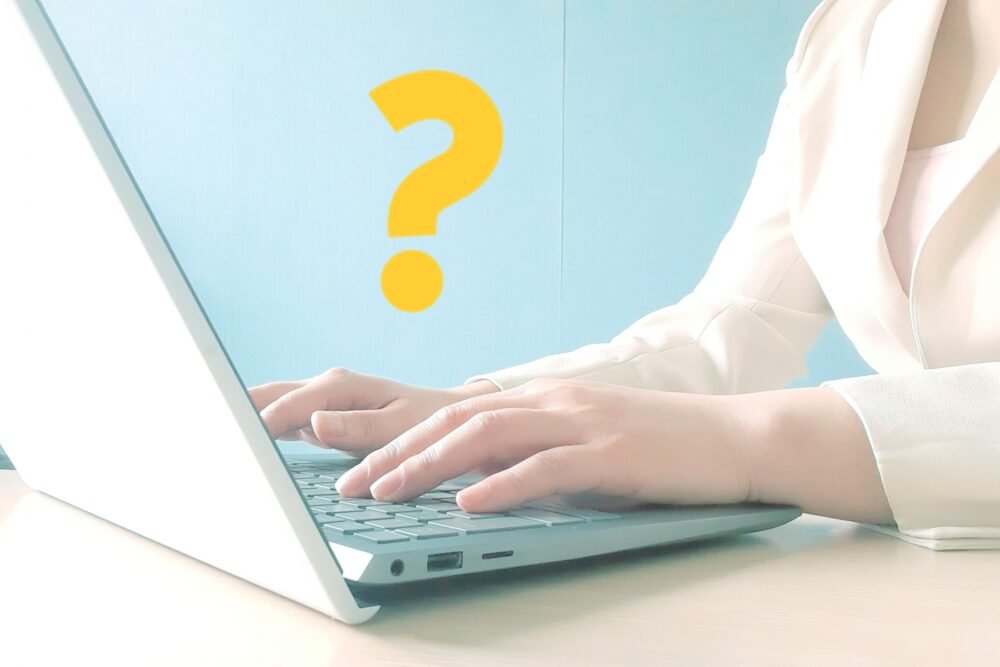PBLとは?取り入れるにあたってメリットとデメリットについて徹底解説!
教育現場で注目を集めている「PBL」。言葉は聞いたことがあっても、どのような内容の学習方法で、どのような効果があるのかまで理解している方は少ないでしょう。
本記事では、PBLとは何か、SBLとの違い、PBLのメリット、デメリットについて解説したうえで、実際の事例も紹介します。
教育現場に携わる方、PBLを取り入れた学びに興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
PBLとは
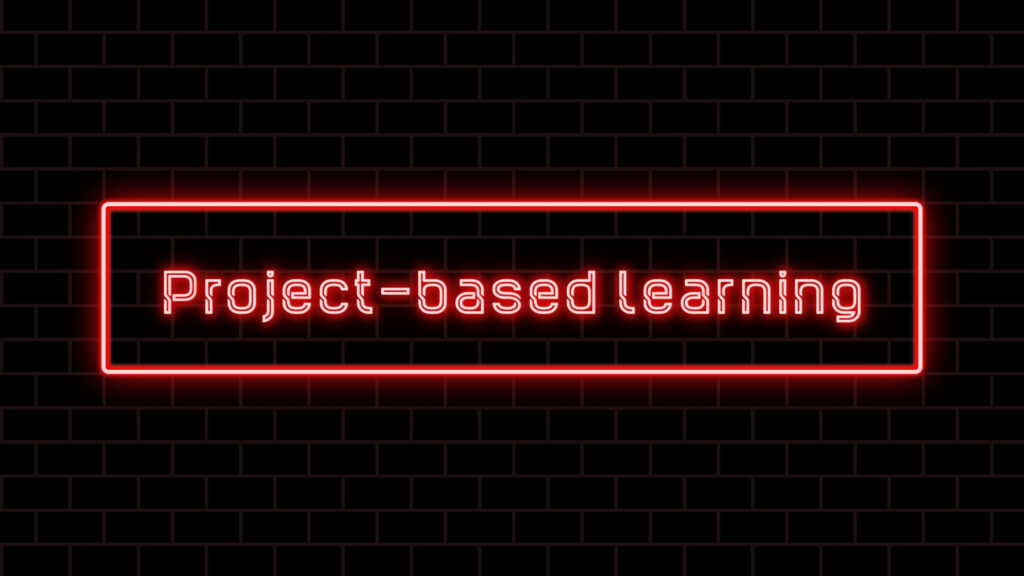
PBLとは「Project Based Learning(プロジェクトベースドラーニング)」の略で、日本語では「課題解決型学習」と訳されます。
1900年代初頭に、アメリカの教育学者ジョン・デューイ氏が提唱したアクティブラーニングの手法で、日本でも文部科学省が教育現場への導入を推進しています。
知識を暗記するだけの受動的な学習ではなく、学ぶ人自身が自分で課題を発見し解決する能力を養う、能動的な学習を目的としています。
この学習方法は、自発性、関心、能動性を引き出すことを重視しており、先生は生徒の能力を引き出すサポート役を担います。
また、PBLにおいて重要なのは正しい答えを導き出すことではなく、その答えにたどり着くまでの過程です。
PBLやPBLに準じた授業を取り入れている大学は多く、開志創造大学 情報デザイン学部もそのうちのひとつです。情報デザイン学部の場合は、扱う課題が架空のものではなく、リアルな課題であるという点がポイントとなっています。
SBLとはどう違う?
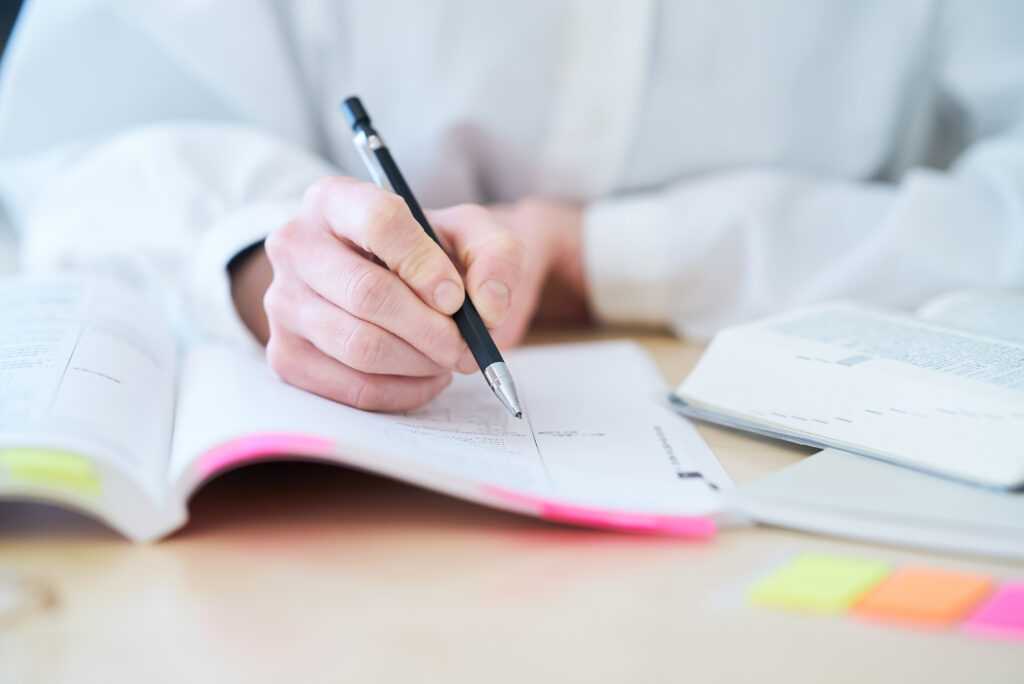
PBLが能動的な学習を促すのに対し、「SBL」は教科書などに沿って先生が主体となって学習を進める手法です。
SBLは「Subject Based Learning(サブジェクトベースドラーニング)」の略で、日本語では「科目進行型学習」と訳される学習方法です。
SBLは物事についての一般的な知識を学習し、原理、構造、使用方法についても理解したうえで、実践的な活用方法に関する問題を解決していきます。
PBLでは課題解決までの過程を重視するのに対し、SBLでは正しく問題を解決することを目的とすることが大きな違いです。
▼PBLとSBLの違い
| PBL | SBL | |
|---|---|---|
| 学習の主体 | 生徒 | 先生 |
| 学習過程 | はじめに課題を提示し、生徒自身が課題解決に必要な知識を学び、考える | はじめに基本的な知識を身につけ、実践のための問題に取り組む |
| 何を重視するか | 課題解決までの過程 | 問題を正しく解決すること |
PBLを取り入れるメリット

PBLを教育現場で取り入れるメリットには、主に以下の5つが挙げられます。
- 能動的な学習であるため、知識が定着しやすい
- 自分で考える力=思考力が身につく
- 身につけた知識を応用する力が養われる
- 自ら調べ、考えることで情報リテラシーが身につく
- コミュニケーションスキルや表現力が養われる
それぞれ詳しく解説します。
知識が定着しやすい
PBLでは生徒が能動的に学習に取り組むため、知識が定着しやすいというメリットがあります。
課題について自ら考え、調べて得た知識は体験として記憶に残りやすいためです。
一方でSBLは先生が主体となり学習を進めるため、能動的な学習であるPBLで得た知識に比べて、生徒の記憶に残りにくいといえるかもしれません。
このように受動的な学習よりも、PBLのように能動的に学んだ知識のほうが定着しやすい点は、大きなメリットといえるでしょう。
思考力が身につく
正しく問題を解決することを重視するSBLとは異なり、PBLは課題解決までの過程を重視するため、その過程で生徒が自ら考える力を養えます。
PBLでは生徒自ら課題に向き合い、考え、情報を集めて整理しなければなりません。課題解決にはさまざまな視点から考えることが必要なため、思考力が鍛えられます。これによって、日常生活でも物事を深く考えることができるようになります。
論理的思考力は、学校での勉強や日常生活だけではなく、将来的にはビジネスシーンでも役立つ重要な能力の1つです。
人生を通して役に立つ論理的思考力が身につくのは、PBLを取り入れる大きなメリットと言えるでしょう。
応用力が養われる
PBLでは能動的に学習し、思考し続けることが求められるため、習得した知識を応用する力も養われます。
SBLのように教科書に沿って基本的な知識を覚えたり、正しく理解したりすることも重要です。しかし、受動的な学習では身につけた知識を柔軟に応用する力を養うのは、難しいと言われています。
課題に取り組む過程で、知識を応用する力が養えるのもPBLのメリットです。
情報リテラシーが身につく
PBLでは提示された課題に取り組むために、自主的に情報を収集し、知識を深めなければなりません。
現代のように膨大な情報に簡単にアクセスできる環境では、正確かつ必要な情報を取捨選択する能力を養うことが情報リテラシーの向上につながります。
情報リテラシーとは単なる情報収集スキルだけではなく、情報社会において情報の真偽やリスクを見抜く力も含まれています。
自分自身を守るうえでも欠かせないスキルでもある情報リテラシーを身につけられるのは、PBLを取り入れるメリットの1つです。
コミュニケーションスキルの向上
PBLでは、課題の解決方法について自分の考えを他の人に伝える機会があります。
どのような知識を応用し、どのように課題を解決するのかを相手にわかりやすく伝えるスキルが向上するのもPBLのメリットです。
PBLのグループディスカッションや発表、プレゼンなどを通して、表現力やコミュニケーションスキルを養うこともできるでしょう。
PBLを取り入れるデメリット
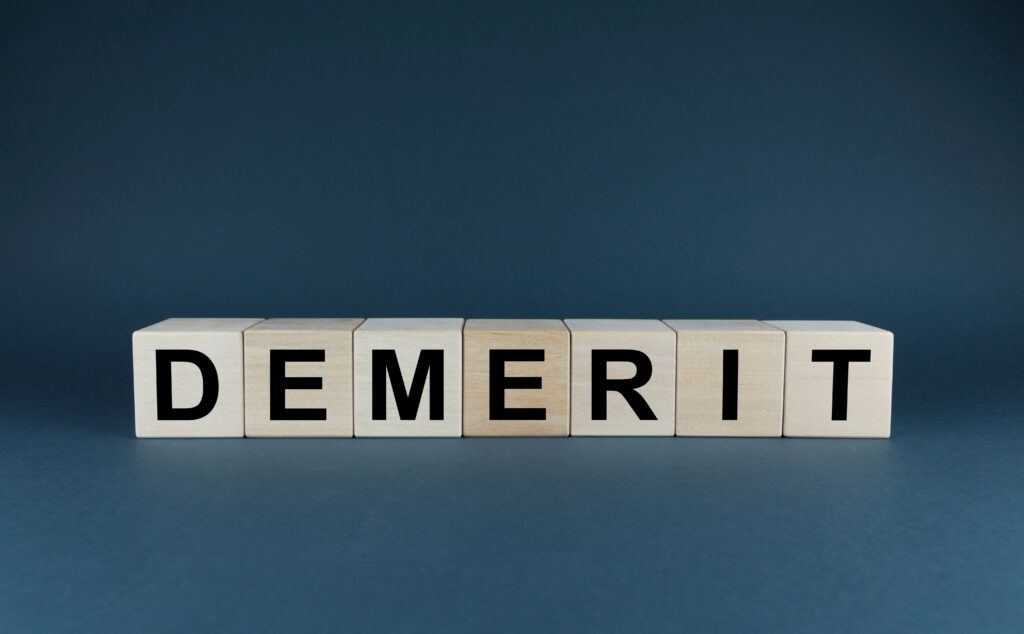
PBLにはさまざまなメリットがありますが、一方でデメリットもあることを理解しておく必要があります。
- 指導の難易度が高く、先生に高いスキルが求められる
- 学習効果の予測や評価がしづらい
- 授業に時間がかかる
- 教科書やカリキュラムと整合性をとりづらい
- すべての生徒に同様の効果があるわけではない
ここでは、PBLのデメリットについて解説します。
指導の難易度が高い
PBLでは生徒の自主性を高められるように、先生は適切なサポートをしなければなりません。教科書に沿った指導ではないため、指導はより難しく、高度なスキルが求められます。
そのため、先生のスキルによって学習の質に大きな差が出てしまうのは、PBLのデメリットと言えるでしょう。
学習効果の予測と効果がしづらい
PBLは、生徒の学習効果や反応を予測するのが難しい学習方法です。また、学習結果として生徒を評価するのが難しいというのもPBLのデメリットと言えるでしょう。
SBLであれば、あらかじめ難易度が高いポイントを押さえながら授業できるのに対し、PBLはあくまで生徒主体の学習であるため、どのような反応や効果が得られるかは実際に授業を始めるまでわかりません。
また、SBLのようにテストの点数で評価がつけられないのもPBLのデメリットです。何を評価基準にするのか決めるのが難しく、先生としては生徒の評価に苦労することもあるでしょう。
授業に時間がかかる
PBLは課題解決のために試行錯誤を重ねる必要があるため、1つの課題に対して多くの時間を要します。
効率的に知識を身につけたい場合や、教えるべき内容が多い場合には、PBLよりもSBLのほうが適していると言えるでしょう。
授業に時間がかかるのは、PBLのデメリットの1つです。
教科書やカリキュラムとの整合性がとりづらい
PBLでは生徒の主体性を重視するため、教科書やカリキュラムとの整合性をとるのが難しいことがあります。
そのため、PBLを実施する際には、事前に教科書やカリキュラムの見直しをしなければなりません。
また、PBLを実施する場合は他の教科や科目と連携することも重要です。PBLを取り入れるためには教育機関全体で協力体制を整えなければならないため、授業時間外にかかる手間が多くなるのはデメリットと言えます。
すべての生徒に効果があるわけではない
PBLはすべての生徒に必ずしも高い効果をもたらすわけではなく、場合によっては十分な成果を得られない生徒もいることがデメリットです。
主体的な行動や自主的な学習が苦手で、協調性がなく、協働作業が苦手な生徒にとっては、PBLの教育効果が十分に発揮されにくい可能性があります。
PBLは生徒自身の興味関心に基づいた課題に取り組むことが大切ですが、生徒自身が自主的に興味関心のある課題を見つけられるとは限らないため、その点にも注意が必要です。
教育機関で行われたPBLの事例

教育機関で実際におこなわれたPBLの事例を3つ紹介します。
- 企業連携ワークショップ/早稲田大学
- PBL(Project Based Learning)科目/多摩美術大学
- プロジェクト授業/産業能率大学
それぞれ詳しく紹介します。
企業連携ワークショップ/早稲田大学
早稲田大学では学生チームが企業や社会の抱える課題に対して解決策を考案し、連携先の経営層に直接提案する「企業連携ワークショップ」を実施しています。
企業が抱える実際の課題について、学部や学年を超えてチームを組み、社会人の指導と監修のもと、課題抽出、分析、グループワークなどを通して課題解決に取り組みます。
最終的に連携先の経営層に対して解決策を提案するため、企業と学生の両者にとってメリットを生み出すプログラムです。
PBL(Project Based Learning)科目/多摩美術大学
多摩美術大学では所属学科や学年の枠を超えて、横断的研究や社会的課題に取り組むプロジェクト型の授業を実施しています。
学生が主体的に問題解決に取り組む学修を主体とし、各自の専門性を総合的に活用する能力を身につけます。
異なる専門的なスキル、知識、感性を持つ学生が集まることで、授業を通して触発し合い、幅広く柔軟な考え方や新たな創造を生み出す学びの場です。
科目の構成は、各専門分野に沿った課題提案、企業・自治体・各種団体との産学官共同研究、新たな領域への実験的なものなど、実践的で多彩な内容になっています。
プロジェクト授業/産業能率大学
産業能率大学では、経営の学びを活かして現実社会の課題に挑む授業を実施しています。
ハイレベルな課題解決を可能にする理論とスキルの修得を目指し、PBLを通じて学生が現実社会の課題に挑む授業です。
チームで課題に取り組み、企業や地域の方から評価を受けます。
PBLで課題解決力を身につけたいなら、開志創造大学 情報デザイン学部
開志創造大学 情報デザイン学部は2026年4月に開設する通信教育課程の学部です。通学の必要がなく、完全オンラインで大学を卒業することができるため、自分のペースで学修を進めながら、大学卒業の証である「学士(情報学)」の取得を目指すことができます。
情報デザイン学部では、さまざまな企業と連携して実際のビジネス現場の課題を扱う「PBL授業」を実施します。課題の解決を目指していくなかで「実践力」や「課題解決力」などが身につきます。
PBL授業では学生同士でチャットを用いてディスカッションをおこないます。オンライン上でのディスカッションは、対面よりも自分の意見を相手に伝えるのが難しくなります。しかし、難しい分「思考力」や「表現力」なども養うことができます。
社会全体で必要とされているITスキルを身につけることはもちろん、ビジネス現場における課題解決やプロジェクトの進行などを実践的に学びたい方は、ぜひこちらもご覧ください!
まとめ

従来の受動的な学習とは異なる教育方法として注目を集めているPBL(Project Based Learning)。生徒の自主的な思考力を養う効果が期待できる教育方法で、日本でもさまざまな教育機関で取り入れられています。
従来のSBL(Subject Based Learning)は教科書やカリキュラムに沿って知識を身につける教育方法でしたが、PBLは生徒が自主的に課題を発見し、解決する能力を養います。
正しく問題を解決することを重視するSBLに対し、PBLは課題解決までの過程を重視することが特徴です。
PBLにはメリットとデメリットがあります。
生徒と先生どちらもメリットとデメリットを理解し、PBLに臨むことが大切です。