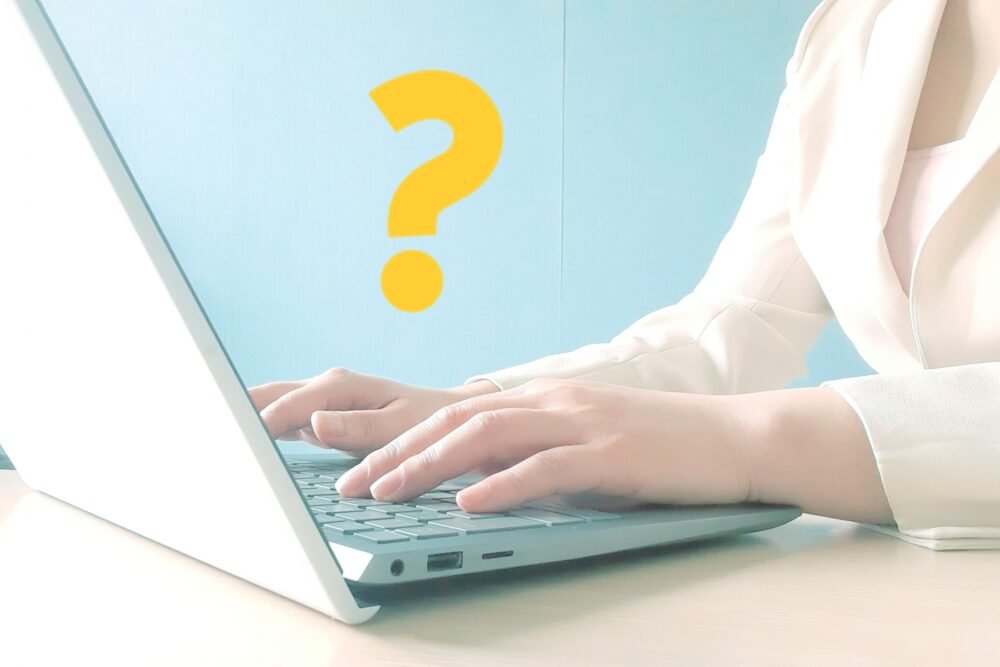アントレプレナーシップとは?求められるスキルや事例を徹底解説!
現代の日本企業で求められる「アントレプレナーシップ」。リスクや課題に立ち向かい新たな挑戦をする人や、その姿勢・行動を指す言葉として、徐々に広まり始めています。
本記事では、アントレプレナーシップとは何か、求められる理由、発揮する人の特徴について解説しつつ、実際にアントレプレナーシップが発揮された企業の事例やアントレプレナーシップを発揮するための教育方法についても紹介します。
企業で働く人も、雇用する側の人も、ぜひ最後までご覧ください。
目次
アントレプレナーシップとは?

アントレプレナーとはフランス語で「仲介人」「貿易商」を指す単語です。ビジネスシーンでは特に「0から事業を立ち上げる人」「起業家」という意味で使われます。
アントレプレナーシップはアントレプレナーの精神、つまり「起業家精神」を指す言葉です。
アントレプレナーシップにはさまざまな定義があります。
例えば小学館は「新しい事業の創造意欲に燃え、高いリスクに果敢に挑む姿勢」、アメリカのハーバード・ビジネス・スクールのハワード・スティーブンソン教授は「コントロールできる経営資源を超越し、機会を追求する姿勢」と定義づけています。
表現の違いはありますが、いずれもアントレプレナーシップのことを「新たな物事に挑戦する姿勢」などと定義していることは共通です。
またアントレプレナーシップは必ずしも起業家だけが持つものではなく、企業や商品開発のリーダー、老舗で変革を試みる後継者、起業を目指す学生なども持っているものです。
簡単に言えば「新たな挑戦をする人」「新たな試みのためにチームや組織を引っ張る人」などは、アントレプレナーシップがあるといえます。
アントレプレナーシップが求められる理由

日本においてアントレプレナーシップが求められる理由として、日本の低下した国際競争力の回復と変化する日本企業の雇用形態への対応が挙げられます。
ここでは、アントレプレナーシップが求められる2つの理由についてそれぞれ解説します。
アントレプレナーシップを持つ人材の不足
日本企業ではアントレプレナーシップを持つ人材が不足しており、そのことが国際競争力の衰えにも大きく影響しています。
国際競争力の指標の1つとして、国際経営開発研究所(IMD)が公開している「世界競争ランキング(The 2024 IMD World Competitiveness Ranking)」を見てみましょう。

出典:IMD「世界競争力年鑑2024」からみる日本の競争力 第1回:データ解説編
1992年までは1位だった日本のランクは徐々に下がり、2024年時点では38位で過去最低になりました。
各国の評価基準項目は約300項目ありますが、特に「ビジネス効率性」の分野で日本の評価順位が低かったのは「経営プラクティス(65位)※」や「生産性・効率性(58位)」、「取り組み・価値観(57位)」などです。
また、かつて日本の強みであったインフラ分野においても、「基礎インフラ(41位)」など、年々下降しています。
下降する日本のビジネスが国際競争力を取り戻すには、新しい価値を見出す考え方や姿勢、新たな挑戦ができる人材の存在、つまりアントレプレナーシップを持つ人材が必要であると考えられているのです。
※経営プラクティスとは、組織を目標達成へ導くためのマネジメントの指標とされている14の項目のことであり、その指標をどれだけ達成できているかを評価する項目
参考:IMD World Competitiveness Booklet 2024
雇用側に求められる変革
積極性や創造性が求められる現代では、企業内で働く個人にとってもアントレプレナーシップが重要な役割を果たします。
終身雇用や年功序列などの日本型雇用システムといわれる仕組みが崩壊しつつある今、個人がアントレプレナーシップを持つ重要性が増しています。
指示を待って動くだけの人材よりも、自発的に課題を見つけ、新たなビジネスに気づき行動し、結果を追求できる人材が求められているのです。
アントレプレナーシップを発揮する人の特徴

アントレプレナーシップを発揮する人には、以下のような特徴があります。
- リスクとポジティブに向き合える
- マネジメント能力と統率力がある
- 課題や問題の発見とその解決のために動く
- 学び続ける姿勢を持っている
それぞれ詳しく解説します。
リスクとポジティブに向き合える
アントレプレナーシップを発揮する人は、あらゆるリスクに対してポジティブに向き合います。
リスクをネガティブに捉えすぎず、成功体験も含めた過去の事例にとらわれず前向きに挑戦する姿勢でいることが大切です。
リスクに怯えて動かないのではなく、リスクを踏まえて対策しながら行動を起こせるかが、アントレプレナーシップを発揮するためには欠かせません。
マネジメント能力と統率力がある
アントレプレナーシップを発揮する人は、マネジメント能力や統率力に優れているという特徴があります。
自分が定めた目標に向かって、メンバーを巻き込みながら管理します。
マネジメント能力や統率力があれば、新たな挑戦の中でもメンバーとともに物事を上手く進められるでしょう。
課題や問題の発見とその解決のために動く
自分の中で課題や問題を発見したり、その課題の解決のために動ける人もアントレプレナーシップを発揮する人の特徴です。
具体的には、勤めている企業や社会などに対して問題意識や課題を発見できるだけに留まらず、行動を起こせることなどが挙げられます。
また課題や問題解決のために粘り強く動き続けられる忍耐力があることも、アントレプレナーシップを発揮するために必要な姿勢の1つです。
学び続ける姿勢を持っている
アントレプレナーシップを発揮するには、新しい物事を学び続ける姿勢が欠かせません。
常に最新の情報にアンテナを張り、必要な学びを続けることで社会に遅れをとらず、最先端で活躍できるからです。
またアントレプレナーシップを発揮する人は新しい物事に抵抗を持たず取り入れ、手に入れた情報を積極的に活用する傾向にあります。
アントレプレナーシップが発揮された企業【3選】

実際にアントレプレナーシップが発揮された企業の事例を3つピックアップして紹介します。
- 株式会社リクルート
- 株式会社スマイルズ
- 株式会社LIXIL
株式会社リクルート
株式会社リクルートでは、積極的に社内ベンチャーを設立し数多くの社会問題の解決を果たしています。
基本理念に「私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。」を掲げる同社は、アントレプレナーシップを発揮しやすい場所であると言えるでしょう。
例えば、グループ会社であるリクルートマーケティングパートナーズ(2012〜2021年)は地域差や所得差による教育格差問題の解決のために「受験サプリ(現スタディサプリ)」を開発しました。
社会問題に着目して今までにない新たなサービスを提供することで事業としての成功を収めた、アントレプレナーシップが発揮された事例です。
株式会社スマイルズ
株式会社スマイルズは、三菱商事が初めて設立した社内ベンチャーです。立場や役職に縛られず、社員が個々にプロジェクトや事業を責任をもって進行することを推奨しており、アントレプレナーシップを発揮しやすい環境になっています。
同社でアントレプレナーシップが発揮された事例としては、女性をターゲットにしたスープ専門店「Soup Stock Tokyo」が挙げられます。
「Soup Stock Tokyo」は1999年に第一号店を出店し成功させ、社内ベンチャーとして独立を果たしました。現在は首都圏を中心に約50店舗を展開しており、雑貨屋など他ジャンルの事業にも乗り出しています。
アントレプレナーシップを発揮し社内ベンチャーとして事業を開始し、新たなビジネスを成功させた事例です。
株式会社LIXIL
住宅設備メーカーである株式会社LIXILでは、新規ビジネス部門で「車いすユーザーが自由に玄関ドアを開閉できる電動ドアオープナー」の開発をおこないました。
車いすユーザーに向けたドアオープナーの開発は同社が長年抱え続けてきた課題でしたが、ソニー株式会社の事業支援サポート(Sony Startup Acceleration Program)と協力しながら開発を推し進め、約1年の期間を経て2020年に電動オープナーシステム「DOAC」の発売を開始するに至っています。
長年抱えてきた企業内の課題を、外部の支援を受けながら解決し、新商品の開発と販売を成功させました。
課題の発見と解決のための行動、そして他社の事業支援を受けて学び続ける姿勢がアントレプレナーシップの発揮された事例と言えるでしょう。
アントレプレナーシップの育成方法事例

アントレプレナーシップは、きちんと学ぶことで育てることができます。
ここでは、アントレプレナーシップのための育成方法を3つ紹介します。
- 大学で学ぶ
- ビジネススクールで学ぶ
- 文部科学省の全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムで学ぶ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
大学で学ぶ
大学でアントレプレナーシップを学べるのは一般的に経営学、商学、ビジネス学、法学、経済学、総合政策学、教養学などの学科です。
また東京大学など一部の大学ではアントレプレナーシップの教育を専門的におこなっており、起業やスタートアップに関する講義や講座の実施、初歩から順を追って学ぶためのプログラムを提供したりしています。
近年では特にビジネス分野においてアントレプレナーシップに注目が集まっていることもあり、大学教育の中でも起業家精神の育成や新たな価値を創造できる能力を持った人材の育成が積極的におこなわれています。
ビジネススクールで学ぶ
ビジネススクールで実施しているMBAプログラムでも、アントレプレナーシップを身につけることが可能です。
MBA取得には、実際の企業実例を用いた実践的な学習が必須です。様々な企業の事例を研究(ケーススタディ)することで、アントレプレナーシップの基礎となる思考を身につけたり、メンバーをどうマネジメントし導いていくべきかなどを解像度高く学んだりすることができます。
ビジネススクールでの学習では、こういったマネジメント能力や統率力といったアントレプレナーシップを発揮するときに欠かせないスキルを身につけることが可能です。
文部科学省の全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムで学ぶ
アントレプレナーシップが重要であるという考えのもと、文部科学省では積極的なアントレプレナー育成事業に乗り出しています。
全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムではさまざまなイベントを実施しており、学生や教職員に向けて有益な情報を発信しています。
例えば2024年11月に文部科学省主催で行われた特別講演では「アントレプレーシップ×失敗学」をテーマに、積極的な失敗の推奨とその失敗から学びを繰り返すことの大切さを説いています。
このようなトライアンドエラーの精神と学び続ける粘り強さはアントレプレナーシップにおいて重要な姿勢です。
立場や目的に合わせた情報を閲覧でき、実際にプログラムに参加することでアントレプレナーシップを身につけることができるでしょう。
アントレプレナーシップを身につけるなら、開志創造大学 情報デザイン学部がおすすめ
開志創造大学 情報デザイン学部は2026年4月に開設する通信教育課程の学部です。一度も通学せずに、卒業時には大学卒業の証である「学士(情報学)」を取得することができます。
授業は1回15分とコンパクトなため、いつでもどこでも自分の都合に合わせて学ぶことが可能です。
情報デザイン学部には「情報技術」×「デザイン」×「経営基礎」の3つの学びがあります。
本コラムで解説をした「アントレプレナーシップ」もカリキュラムに含まれる予定となっており、その他にも「デジタルマーケティング」や「コーポレートファイナンス」などを学ぶことで、経営基礎の知識を養うことができます。
これからの時代に必要不可欠な情報技術に関する知識に加え、アントレプレナーシップなどの経営基礎の
力を身につけることで、情報技術を活用して、情報社会における課題解決と価値創造ができる能力を身につけた人材を目指します。
今回の記事で取り上げたアントレプレナーシップなどの学びに興味のある方には、情報デザイン学部がおすすめです!
まとめ

国際競争力が衰える一方となった現代の日本のビジネス現場において、強く求められている「アントレプレナーシップ」。問題や課題を発見し、リスクに立ち向かい新たな挑戦をする人やその姿勢を指す用語です。
実際にアントレプレナーシップを発揮したことで社会の問題や課題を解決したり、事業を成功させたりしている事例は多々あります。
体系的にアントレプレナーシップを身につけたいなら、大学やビジネススクールに通ったり、文部科学省の育成プログラムを受けたりすると良いでしょう。
これからの社会で求められる人材になるために、アントレプレナーシップを身につけませんか?