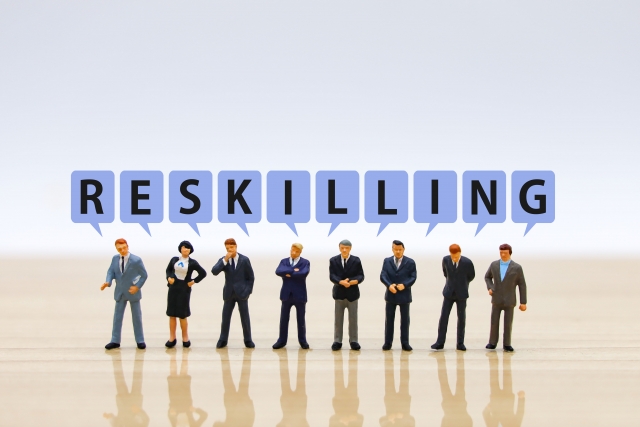アンラーニングの意味とは?リスキリングとの違いやメリット、やり方のステップを解説
過去の知識やスキルを見直し、時代に合わせた新たな知識とスキルを身につける学習方法である「アンラーニング」。
現在身についている知識やスキルを意図的に捨てるという大胆な学びの形ですが、社会人にとって重要な意味があるとして注目を集めています。
本記事では、そんなアンラーニングについて、アンラーニングとは何か、リスキリングとは何が違うのかを解説したうえで、注目されている理由や実施するメリット、注意点、実践の手順についてもお伝えします。
目次
アンラーニングとは?

アンラーニング(Unlearning)とは、「学習棄却」や「学びほぐし」といった意味の言葉です。
これまでに修得した知識やスキルを一度捨て、新たに学び直すことを指します。
時代の変化や新たな知識などを修得することで、知識をアップデートすることができ、仕事においても業務効率の向上や成長促進などの効果が狙えます。
アンラーニングについて、青山学院大学の松尾睦教授は「個人が自身の知識やスキルを意図的に棄却しながら、新たな知識やスキルを取り入れるためのプロセス」と定義しました。(参考:仕事のアンラーニング/松尾睦)
ビジネスにおいては、優秀な人材ほど時代遅れになってしまうケースが多く、アンラーニングはこういった「有能さの罠(コンピテンシー・トラップ)※」への対策として有効と考えられています。
※:有能さの罠(コンピテンシー・トラップ)とは、ビジネスにおいて過去の成功に固執して広い視野を持てなくなること、また新たな行動を起こせなくなることを指します。
アンラーニングとリスキリングの違い

アンラーニングに似た言葉で、社会人の学びに関するものには「リスキリング」も挙げられます。
リスキリングとは、「スキルの再習得」「学び直し」を意味する言葉で、「新たな知識やスキルを獲得すること」に焦点を置いています。
一方、アンラーニングは「過去の知識やスキルを見直しつつ新たな知識やスキルを学び、取捨選択すること」に焦点を置いています。
アンラーニングは過去に積み上げた知識、スキル、成功体験を整理しつつ、ビジネスの現状に合わないものを捨てたり新たな領域に踏み込んだりする学習方法です。過去に積み上げたものも見直し、今後に向けて本当に必要なものだけを手元に残すことを目的としている点がアンラーニングの特徴と言えるでしょう。
アンラーニングを学習するための土台をつくり、リスキリングでさらにレベルの高い知識やスキルの修得を目指すと考えるとイメージしやすいかもしれません。
アンラーニングとリスキリングを組み合わせることで、効果的な学習が可能になるでしょう。
リスキリングについては、「リスキリングとは?補助金・助成金など個人向けのリスキリング支援を一挙紹介! |」で詳しく解説しています。気になる方はぜひ併せてご覧ください。
アンラーニングが必要とされている理由

アンラーニングが必要とされている理由として、激しい時代の変化が挙げられます。
情報化社会とも言われるように情報であふれている現代では、デジタル技術を中心として激しい変化が常に起こり続けています。
そんな中で、過去の知識やスキル、成功体験に頼りきっているといつまでも時代遅れのビジネスを続けてしまうことになりかねません。
そこでアンラーニングを実施することで、過去や現在のやり方にとらわれず新たな知識やスキルに目を向け、取り入れることができます。
アンラーニングを実施し、常に最新の情報にアンテナを張ることで、効率的な業務を行うことや新たなビジネスチャンスの獲得が可能になるのです。
アンラーニングのやり方3ステップ
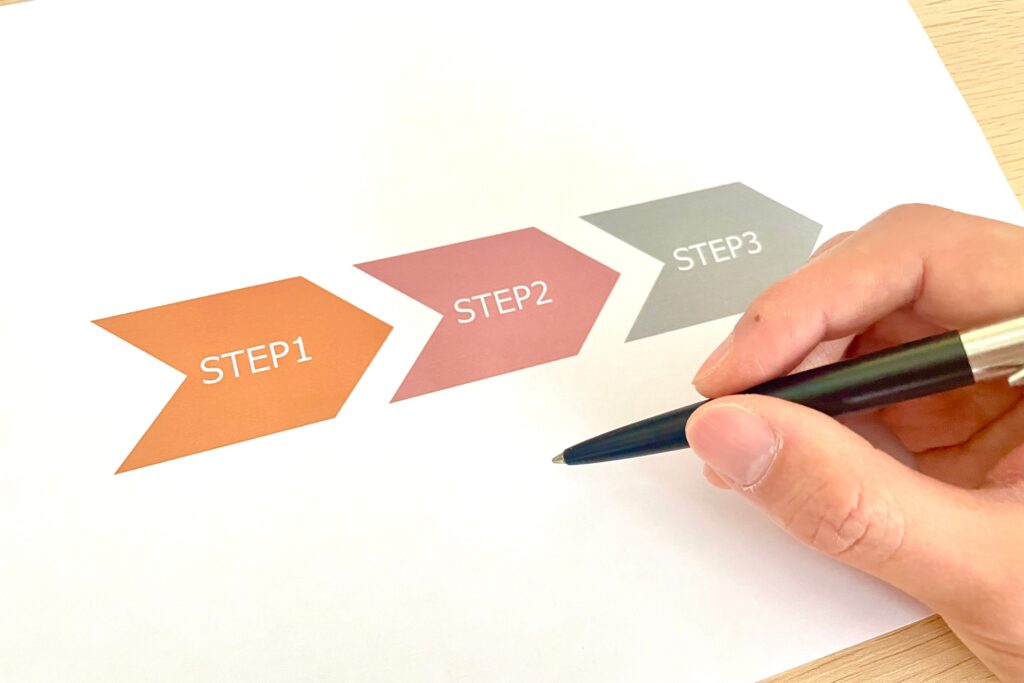
アンラーニングを実施する際は、大きく分けて3つのステップがあります。
- 今持っている知識やスキル、経験を振り返る
- 過去の経験を踏まえて、必要なものを選ぶ
- さらに身につけるべき知識やスキルについて学びを進める
各ステップについて、それぞれ詳しく解説します。
1.自分自身の知識、スキル、経験を振り返る
ステップ1では、現在自分が持っている知識、スキル、経験について振り返ります。内省の目的は、自分が持つ知識、スキル、経験などが新たな学びの妨げになっていないか気づくことが目的です。
知識、スキル、価値観、こだわり、成功体験、失敗体験などを書き出すなどし、さらに他者との比較や客観的な視点などを通して整理しましょう。
振り返り作業は一人で行うよりも、交流会やワークショップに参加したほうが外部からの刺激や客観的な視点を得やすいため捗るのでおすすめです。
2.選択をする
ステップ1で洗い出した知識、スキル、経験などを整理し、今後も必要なものと不要なものに分けていきます。
必要と判断する基準としては、「現代のビジネス環境に適しているか」「社会的に需要があるか」「他者にとっても価値のあるものか」など具体的なポイントを設けるのがおすすめです。
逆に、不要なものについても「他者や社会のために活かせるか」「現在のビジネスにおいて活用可能か」などのポイントをしっかり設定しましょう。
選択のステップでも客観的視点は重要なため、チームメンバーや上司などから積極的にフィードバックを受けるようにしてください。
3.新たな学びを進める
最後のステップでは、実際に行動や価値観を変え、新たな学びを進めていきます。
継続的に異なる価値観を持つ人と交流したり、情報を仕入れられる環境に身を置いたりすることで自然と価値観や知識、スキルのアップデートができるでしょう。
知識やスキルはテキストなどで学ぶことが可能ですが、価値観を変えたり体験・経験を積んだりするには時間を要します。焦らず、確実に自分自身をアップデートしていくことを意識することが大切です。
【企業向け】アンラーニングを推進するメリット

ここでは、企業目線でアンラーニングを実施するメリットとして、主に以下の3つを挙げてご紹介します。
- 人材育成において高い効果が期待できる
- 業務効率の向上が期待できる
- 組織全体が変化に対して強くなる
それぞれ詳しく解説します。
人材育成での効果
アンラーニングを実施することで、人材育成において高い効果が期待できます。
経験豊富な従業員や、既に十分なスキルや知識を持っている人材は新たな学びに対して消極的で、昔のままアップデートできていないケースが多くあります。
そこでアンラーニングを実施することで、今までの知識やスキル、経験を整理したうえで今後必要な新たな情報を仕入れることができるでしょう。
リスキリングを実施する前にアンラーニングをおこなえば、従業員もすでに知っている情報や体験にとらわれることなく、スムーズに新たな学びを進められるようになります。
新人ではなくベテラン従業員などを中心にアンラーニングを実施すると、人材育成に高い効果が期待できるのです。
業務の効率化
アンラーニングを実施すると、業務効率の向上が期待できます。
既存の業務はベテラン従業員を中心に、昔から継続しておこなってきた業務フローに従っているケースが多いです。
アンラーニングを実施して従業員の知識、スキル、経験、価値観を見直したり新たに学ぶ機会を作ると、既存業務に対しても見方が変わるでしょう。
無駄を減らし改善することができれば、業務自体の効率もアップすることが期待できます。
ただし、アンラーニングによる業務改善は一時的に効率が下がることがあるため、注意が必要です。新しいやり方に慣れるまでは時間がかかるため、多少時間がかかっても効率化が見込めるのであればそのまま続行するようにしてください。
組織の意識改革
アンラーニングを実施している組織は全体の意識が変わり、変化に対して強くなります。
アンラーニングを通して取捨選択に慣れ、新たな学びにも柔軟になるでしょう。変化の激しい時代では、組織全体の意識改革が欠かせません。
変化に強い組織であればあるほど、変わりゆく時代の中でも常に対応し続けることができるでしょう。
意識だけでなく、アンラーニングでは具体的な学びを通して実際の業務にも良い効果が期待できます。
組織にとって、アンラーニングは意識面でも業務効率化の面でもメリットがあるのです。
【企業向け】アンラーニングを推進する上での注意点

アンラーニングにはさまざまなメリットがありますが、以下のような注意点があります。
- モチベーションが低下する可能性がある
- 1人ではなくチームで行う必要がある
それぞれ詳しく解説します。
「学習棄却」によるモチベーションの低下
アンラーニングでは、自分にとって慣れた仕事のスタイルを変えたり、今までに培ってきた知識やスキルをなくすステップがあり、モチベーションの低下につながる可能性があります。
従業員によっては「自分の今までの知識や行動を否定された」と感じてしまうこともあるでしょう。
モチベーションの低下に伴い、業務においても一時的にパフォーマンスが落ちてしまう可能性も考えられるため、事前にしっかり説明を行ったりサポートを充実させたりするなどして対策しておくことをおすすめします。
1人ではなくチーム単位で行う
アンラーニングを実施する際は、1人で行うのではなくチーム単位で実施しましょう。
個人でアンラーニングを実施すると、一緒に業務に携わる人に迷惑がかかる場合があるためです。チーム単位でアンラーニングを実施すれば、個人ではなく組織としての意識改革やアップデートがスムーズに進められるので、アンラーニングは必ずチームで実施してください。
またチームでのアンラーニングでは、全体に課題意識を共有し、業務の優先順位や重要度などを最初に整理してから始めましょう。
アンラーニング・リスキリングをするなら、開志創造大学 情報デザイン学部
開志創造大学 情報デザイン学部は完全オンラインで大学を卒業できる、通信教育課程の学部です。卒業時には、通学制の大学と同等の大学卒業の証である「学士(情報学)」を取得することが可能です。
多様化・情報化する現代社会で必要な情報に関する知識や技術を、年間授業料25万円で身につけることができます。
大学となると、どうしてもネックになってしまう学費ですが、4年間通っても比較的安価に抑えることができるので、働きながら学びたいという方にもおすすめです。
情報デザイン学部には、AIなどの最新の情報技術を駆使するエンジニアを目指す「先端ITコース」とビジネス現場を知り課題をITで解決できる人材を目指す「ビジネスITコース」の2つのコースがあり、自分の目指す将来像に合わせて選んで学ぶことができます。
自分の知識やスキルを見つめなおし、今必要とされる知識を完全オンラインの情報デザイン学部で身につけませんか?
まとめ

社会人が自分の持つ知識、スキル、体験などを見直し、情報を取捨選択して新たな学びへ繋げる「アンラーニング」。
アンラーニングを実施すると、変化の多い現代に対応しやすくなるとともに、業務の効率化などのメリットもあります。
一方、アンラーニングを実施すると一時的に効率が落ちたり個人のモチベーションが低下したりするといったデメリットもあるため、注意が必要です。
メリットとデメリット、また実施のステップを理解したうえで、組織の意識改革や業務効率化を目指してアンラーニングを実施してみましょう。